アディクションとコミュニティ⑵
はじめに
前回の講義では、グレゴリー・ベイトソンの帰謬法という手法を用いて、アディクションの問題を考えてみました。ベイトソンによると、エラーがあるのはアディクションの〈醒め〉の部分であり、〈酔い〉はそのエラーを修正するものだということでした。
〈醒めている〉状態にエラーがあるのだとしたら、〈醒めている〉状態の日常生活にエラーの要因が含まれているのだということになります。つまり、エラーの要因は近代社会という社会形態や近代家族という家族形態に含まれるということになるのです。
近代社会(家族)がなぜアディクションを引き起こすのでしょうか。そのことを改めて考えながら、歴史的に最初にアディクションからの回復に力を与えたとされるアルコホーリクス・アノニマス(Alcoholics Anonymous 以下AA)と呼ばれるセルフヘルプグループ(自助グループ)を取り上げ、なぜAAというコミュニティはアディクションを回復に導くのかを、考えてみたいと思います。
AAとは
AAとは国際的なセルフヘルプグループ(セルフグループ・Self Help Group)です。1935年、米国で誕生しました。AAの誕生については、野口裕二(1996)が的確にまとめているので、それを引用します。
AAの誕生は、ビルとボブの伝説的な出会いに始まる。1935年、ニューヨークの株式仲買人ビルは、仕事でオハイオ州アクロンに赴く。そこで仕事がうまくいかずに、「また飲み出すかもしれない」という不安にかられる。(中略)このとき、彼は「自分を救うために、もうひとりのアルコホリック(Alcoholicアルコール依存症者)にメッセージを運ぶべきだ」と突然悟る。そのもうひとりのアルコホリックが、アクロンの医者ボブだったのである。/ボブはビルとの出会いを次のように述べる。「もっともたいせつなことは、彼がアルコホリズム(Alcoho-lism アルコール依存症)に関連して、自分の話していることを体験によって知っている、これまで私と話した最初の生きた人間だったことである。いいかえれば、彼は私のことばを話したのである」。この出会いがAAの誕生の時とされている。(野口裕二『アルコホリズムの社会学』)
ここで重要なことは、「自分を救うために、もうひとりのアルコホリックにメッセージを運ぶべきだ」と悟ったことです。そのメッセージは体験の共有であり、もうひとりのアルコホリックにとっては、「彼は私のことばを話したのである」と受け取られたということです。メッセージは一方的なものではなく、メッセージが伝えられる相手にとっても、自分のことばが他者によって語られるという、個人の壁を超える行為となったのです。
このようにして誕生したAAは歴史的に最初に成功したセルフヘルプグループとなりました。そして現在、130カ国以上に200万人の会員を要する世界的な規模のグループに成長しています。AAの目的はただひとつです。それは飲酒しないで生きることです。その目的を達成するためにAAでは、「12のステップ」という考え方を提示しています。
12のステップの構成は、①自分の無力を認め、②自分を超えたところの絶対的な存在を信じ、③これまでの生活を振り返って自分の短所を見出し、④傷つけた人たちへの罪ほろぼしを考え、⑤仲間に回復の道を示す、の5段階になります。12のステップとは以下の通りです。(原点になった12のステップから多少の言い回しや訳の違いやアディクションの形態によって差異はあります)
1 われわれはアルコールに対し無力であり、生きていくことがどうにもならなくなったことを認めた。
2 われわれは自分より偉大な力が、われわれを正気に戻してくれると信じるようになった。
3 われわれの意志といのちの方向を変え、自分で理解している神、ハイヤー・パワーの配慮にゆだねる決心をした。
4 捜し求め、恐れることなく、生き方の棚卸表を作った。
5 神に対し、自分自身に対し、もう一人の人間に対し、自分の誤りの正確な本質を認めた。
6 これらの性格上の欠点すべて取り除くことを神にゆだねる心の準備が、完全にできた。
7 自分の短所を変えて下さい、と謙虚に神に求めた。
8 われわれが傷つけたすべての人の表を作り、そのすべての人たちに埋め合わせをする気持ちになった。
9 その人たち、または他の人びとを傷つけない限り、機会あるたびに直接埋め合わせをした。
10 自分の生き方の棚卸しを実行し続け、誤った時は直ちに認めた。
11 自分で理解している神との意識的触れ合いを深めるために、神の意志を知り、それだけを行なっていく力を、祈りと黙想によって求めた。
12 これらのステップを経た結果、霊的に目覚め、この話をアルコール中毒者に伝え、また自分のあらゆることに、この原理を実践するように努力した。(野口前掲書より)
AAでは、先行く仲間が、プログラムをスタートして間もない依存症者とペアになって、回復のお手伝いをします。もちろん先行く仲間は回復へのプロセスにある人であり、回復した人です。アディクションの回復とは生き方の修正であり、そのモデルはセルフヘルプグループという、同じ問題を抱えたコミュニティのなかにいる、生身の社会的身体をもった人から得られるのです。そのセルフヘルプグループの仲間が回復のモデルであり、共感を得られる強力なサポーターであるのです。先行く仲間は後輩の回復モデルとなり、先輩をモデルとして回復に向かったアルコール依存症はいずれ、自分自身が後輩の回復モデルとなるわけです。
日本にAAが紹介されたのは1950年ごろで、AAの日本のはじまりは1975年とされています。また日本の断酒会は、AAのデザインを参考にしつつも、日本人の特質に合わせてAAの匿名性や非組織化、献金性といった原則を取り除いて設立させています。
近代社会(家族)はなぜアディクションを引き起こすのか
現代の生活は、家族においても社会においても、常に少しだけ成績や評価が良くなることが期待されるという傾向があります。現状でいいとか、多少下降してもかまわないという生き方は、現実はどうであれ、理念としてはもちにくいわけです。つまり常に上昇することが求められているといってもよいでしょう。
たとえば、わたしたちの暮らしぶりを少し振り返るだけでも、この上昇志向ということがあきらかになります。沖縄における民衆の家屋は、明治時代までは穴屋と呼ばれる掘っ立て小屋がほとんどであったとされています。それが茅葺の家になり、瓦屋根の家になり、鉄筋コンクリートの家へと変遷しています。掘っ立て小屋から鉄筋コンクリートまで百年もかかっていないのです。世代にすると三世代から四世代でしょうか。それくらいで家屋は大幅に変更されているのです。
一世代前と比べても、暮らしは間違いなく変貌しています。二世代前と比べると、おそらく想像を絶するくらい変貌を重ねていることがあきらかになるとおもわれます。つまりわたしたちの暮らしは、常に上昇することがあたりまえとなっているのです。
上昇することを前提とする生き方は、近代社会においてあらわれた現象です。近代以前の伝統的な社会においては、暮らしの変貌は感じ取ることのできないほどゆるやかなものでした。むしろ暮らしに変貌がないようにして生きてきたのが、伝統的な社会のありかたでした。昨日と変わらない今日、その繰り返しが伝統的な社会においては、求められてきたのです。
親が職人であればその子も同じ職人になるというふうに、世代が変わっても暮らしぶりに変更がないことが求められた社会だったのです。そのような社会では、現状を維持することが求められてきました。現代の視点からみると、不思議な社会のような感がしますが、逆にみると、上昇することが求められない社会だったということができます。親の職業は間違いなく子どもに伝達され、親と同じ生活水準が子どもにも繰り返されたのです。
それを貧困の状況であるとみるかどうかは、視点の問題になってきます。貧困というのは相対的な問題です。社会全体の生活水準が低ければ、貧困という問題は、本質的には発生し得ない問題なのです。社会全体の生活水準が上がり、貧富の差が生じることになると、貧困という問題が社会的に発生するのです。
かつて社会学者のイヴァン・イリイチ[1]は、冷蔵庫を持たなくとも生活のできるメキシコの農家の生活と、冷蔵庫を持たないと生活ができないニューヨークのスラム街の生活と、どちらが貧困なのであろうか、という問いを立てました。本質的な意味において貧困とは、何かが欠けているという欠落感によって生じるものだといえるのです。
伝統的な社会においては、生活水準が上昇しない代わりに、安定した生活がありました。しかも親と同じことを繰り返すだけという、努力を要しない安定した生活なのです。
伝統的な社会に比べ、近代以降の社会では、常に生活水準が上昇することが求められました。生活水準が上昇するということ、それ自体はよいことに間違いはないのですが、問題となるのは、わたしたちが常に生活水準の上昇を前提にして生きていかざるをえないということです。
たとえば急降下する坂道でブレーキの利かないバスから降りたくとも降りることができない、それが近代以降の生き方の問題であるといえるでしょう。個人による選択とか意志ではなく、乗っているバス自体が急降下(急上昇でもかまいません。いずれでも降りることができないという点では同じです)しているのです。個人による選択とか意志ではなく、常に生活水準が上昇することが求められているのです。
そのためわたしたちは、少しだけ興奮状態にあることを日常化しています。伝統的な社会では、興奮状態はごくたまに、しかし爆発的に起こるものでした。爆発的な興奮状態が、一時的に社会の秩序を転倒させ、カオス(chaos)[2]状態を巻き起こします。
カオス状態のなかで人間は個人を離れ、集団的意識と一体化します。そのような状態は社会にとっても個人にとっても危険な状態なので、あくまでも一時的な爆発的興奮状態として秩序づけるのです。それが祭りなどの原初的なスタイルです。しかしこの危険な状態もまた、人間には必要なことだったのです。
たとえば戦前の那覇の大綱引きは殺気立っており、殺人には至らない程度の流血騒ぎがつきものであったいわれています。これは那覇の大綱引きだけにかぎられる現象ではありません。祭りには常に殺気立つような興奮がつきものだったのです。
あえてこのような危険な状態を演出することは、社会集団を維持するために必要とされたことだといえます。このような殺気によって人びとは、日常生活とはことなる「ハレの日」を現出させることができたのです。「ハレの日」は「聖なる日」です。「聖なる日」は殺気によって原初的な荒々しいエネルギーを、社会集団にもたらすことができるのです。
個人が個人の殻を破って集団と交わるのは、人間社会の課題でした。人間には個人に閉じこもりたいという性向と他人を求めるという性向が、分かちがたく結びついています。この個人の殻を破り社会を成立させる(他人を求める)ために、爆発的な興奮状態が必要とされたのです。
伝統的な社会では、そのような興奮状態は、一定のルールとマナーに基づいて奨励されました。興奮状態が社会の基盤を揺るがすことがあってはならないのですが、興奮状態によって個人と社会との融合関係をもたらさなければならなかったからです。
しかし現代の生活において、爆発的な興奮状態は必要のないものとなりました。その代わりに、かすかな興奮状態を日常的に持続させることになってしまいました。一時的な爆発的な興奮状態が、日常的なかすかな興奮状態に変わったとき、爆発的な興奮状態を起こさせる刺激物や刺激が、日常的に服用されるか、爆発的な興奮状態を、規模を小さくして、個人的に繰り返すようになってしまいました。
アルコール、薬物、ギャンブル、恋愛など、個人の殻を超えて爆発的な興奮状態を惹き起こすのに必要だった刺激物や刺激、感情が、集団の行動としてではなく、個人の行動として日常的に使用され、繰り返されるようになります。伝統的な社会においては、一定のルールとマナーのもとに、興奮状態を作り出す刺激や刺激物、感情は、統制されていたのですが、それが個人的な行動となった場合、集団による統制は効かないものとなります。
爆発的な興奮状態を惹き起こす刺激物や刺激、感情は、個人の殻を破るために必要とされたのですから、当初から個人による抑制は期待できないものでした。なぜならそれらは個人の意志や抑制心を取り除くための刺激であったからです。
このような刺激物や刺激が習慣化したとき、人間はこれらに支配されてしまうことになります。それがアディクションといわれるものです。本来、人間の集団において肯定的な評価を受けていた英雄的な行為が個人化したとき、ポジティブなものはネガティブなものへと反転します。
なぜAAというセルフヘルプ・グループはアディクションを回復に導くのか
歴史的に最初にアディクションからの回復に力を与えたのは、AAと呼ばれるセルフヘルプグループ(自助グループ)でした。アルコホーリクスとはアルコール依存症者たちという意味で、アノニマスは「無名の(匿名の)」という意味です。ですからアルコホーリクス・アノニマスとは「無名の(匿名の)アルコール依存症者たち」という意味になります。セルフヘルプグループとは、共通の問題を抱えた者どうしが集まって、支えあっていく集団のことです。その原型は、アルコール依存症者の自助グループAAにあります。
それではAAとは、どのようなセルフヘルプグループなのでしょうか。AAの回復プログラムは、「12のステップ」と呼ばれるものに基づいていますが、「12のステップ」のうち最初の三番目までが重要ですので、最後の12番目のステップとあわせて引用したいと思います。
下記の引用は「日本ダルク」の「NAの12ステップ」からです。アルコールを薬物依存に変えているだけで、視点は同じです。
1 われわれは薬物依存に対して無力であり、生きていくことがどうにもならなくなったことを認めた。
2 われわれは自分より偉大な力が、われわれを正気(健康的な生き方)に戻してくれると信じるようになった。
3 われわれの意志と生命を、自分で理解している神、ハイヤー・パワー(higher power)の配慮にゆだねる決心をした。
(中略)
12 これらのステップを経た結果、霊的に目覚め、この話を薬物依存者に伝え、また自分のあらゆることに、この原理を実践するように努力した。[3]
日本ダルク代表の近藤恒夫氏の記述を引用しながら、この12ステップへの理解を深めたいと思います。
すべて過去形になっていることに注目してほしい。12のステップは、自分がこの段階を実践できたことにあとで気づかされるかたちになっている。[4]
ステップ1の「われわれは薬物依存に対して無力である」というのは、すでに述べた「クスリと闘おうとするな」ということだ。
初めてこのステップ1を聞いたときにはさっぱり意味がわからなかった。「そんなことより、今すぐ覚せい剤をやめる方法を教えてくれ」というのが正直な気持だったし、「オレはそのうち自分の意志の力で覚せい剤をやめてやるんだ」という気負いのようなものもあった。
そのあたりが十分に腑に落ちないまま、とりあえず毎日3回のミーティングには通っていたのだが、相変わらず幻聴、耳鳴りはやまないし、周りの仲間たちに比べても自分の病気がよくなっている実感がさっぱりない。そんな日々が約一年間続いたころ、これではひょっとしたら何年やってもダメかもしれない、というあきらめのような気持がわき上がってきた。同時に、ようやく自分の無力さを認めるということがわかったというのだろうか、現実を認めざるをえない境地に達した。ちょうどそのころから、クスリをやめ続ける精神的苦しさがグッと軽減されるようになった。[5]
自分の意志の力ではアディクションをコントロールすることはできないという「あきらめ」の気持が生じたとき、はじめて現実を受け入れることができ、アディクションから解放されることの苦しさが軽減されるようになるのです。
ステップ2は「自分以外の力が必要だと信じるようになった」ということだ。私の場合、自分のすべての問題を解決してくれるのはクスリだと信じていた。しかし、病院や拘置所を出たあと、仲間たちの話に耳を傾けているうちに、自分は彼らに助けられていると感じるようになり、仲間たちを信じられるようになった。「回復の95パーセントは仲間たちの話を聞くことによる。信じるという漢字は、“人に言う”と書くでしょう」とロイさん[6]は言っていた。[7]
「自分以外の力」とは同じアディクションを共有する仲間です。回復へのプロセスの95パーセントは、「仲間たちを信じ」、「仲間たちの話を聞くこと」によるのです。
ステップ3の「ハイヤー・パワー」と12の「霊的に目覚める」ことについて、近藤氏は次のように説明しています。
「霊的に目覚める」の意味はむずかしい。“霊的”は英語の「スピリチュアルspiritual」だ。人間にはボディ(=身体)があって、マインド(=心や思考)があって、さらに奥の芯の部分にスピリット(=魂あるいは自我)という霊的な何かがあるという考え方から来ている。薬物依存から立ち直るには、身体や精神の回復だけではなく、霊的な部分の回復まで必要だということだ。
これら12のステップは、私たちは自分を超える大きな力に助けられ、生かされており、それに自分をゆだねるべきだという考えを前提にしている。その力を「ハイヤー・パワーhigher power」と呼ぶ。[8]
精神と物質を分離して考えるデカルト的二元論では、「霊的に目覚める」とか「ハイヤー・パワー」などという概念を理解することはむつかしいでしょう。
ここで前回の講義を思い出して見ましょう。生態学者のグレゴリー・ベイトソンは、木を切るきこりや杖に導かれる盲人のたとえで、精神と物質を分離することはできないことを指摘しました。きこりや盲人にとっての自己は、自己の動きを決定する「システム全体のサーキット」の中にしか存在しないとするのです。
この自己の動きを決定する「システム全体のサーキット」を自覚的に対象化することができるのなら、それは自己という存在を超える「ハイヤー・パワー」ということになり、そのハイヤー・パワーに包まれて動かされている自己、あるいは動いている自己を自覚的に対象化できたときは、「霊的に目覚める」ことになるわけです。
第3回目の講義「子どもという存在(2)」では、近代以前のヨーロッパの宇宙観に少しだけ触れました。近代以前、深い森に包まれて生活していたヨーロッパでは、深い森こそがマクロコスモス(大宇宙)であり、人間の世界はマクロコスモスに包まれたミクロコスモス(小宇宙)として存在するという宇宙観がありました。
子どもという存在は、そのマクロコスモスとミクロコスモスをつなぐ媒介として見られていたのです。このマクロコスモスと人間世界との連続性が断ち切られたときに、〈子ども〉は誕生します。逆に見るなら、17世紀末に〈子ども〉という存在が誕生するまでは、西欧社会においても、マクロコスモスに包まれて人間社会は存在していたといえるのです。
このマクロコスモスを物質世界として分離し、ミクロコスモスだけを拡大したのが近代社会だといえるでしょう。その意味で「ハイヤー・パワー」という言葉は、マクロコスモスの復活を告げる言葉だといえます。
近代的自己の解体
AAのプログラムで特徴的なことは、徹底して個人であることを求めるとともに、個人であることにまつわる近代的な意義づけを解体しているということです。近代的自己の解体ということです。
AAのアノニマスという言葉は、「無名/匿名にとどまる」ということを意味しています。「無名/匿名にとどまる」ということは、何をあらわすかというと、名前にまつわる社会的地位を求めないということになります。社会的地位が必要とされないコミュニティにおいては、何が個人をあらわすのかというと、外的な刻印です。
たとえば、タトゥー(刺青)などがそれにあたります。そこではタトゥーが個人をあらわすことになり、タトゥーに表象されたネームで呼ばれることになります。狩猟採集のバンド社会であれ、現代のタトゥーであれ、タトゥーは個人を表象するものであるとともに、本名とは異なるネームであるといえましょう。
タトゥーは外面に刻印され、そのことによって、個人の内面性は表出されます。外面が個人の人格となるのです。そのことによってマクロコスモスとミクロコスモスを隔てていた個人の内面性(近代的自己)は除去されます。外的な刻印によって、自己はマクロコスモスとミクロコスモスと交信し、自己に連続性がもたらされるのです。
アディクションの場合、外的な刻印は、「アディクションである自己」ということになります。AAにおいては、依存症者が「無名/匿名にとどまる」ことにより、「アディクションである自己」という自己を、タトゥーを施すように外的に刻印し外面化します。
そのことは「わたしとは何者か?」という近代的な問いから解放されることを意味します。「わたし」が匿名であるとき、「わたし」は近代的な問いから逃れ、伝統的社会において普遍的にみられた演劇性を獲得することになります。演劇性とは「わたし」の外面化なのです。
たとえばセルヘルプグループでは、「こんにちは、アル中のケンです」と名乗ることからはじめます。そうすると会場からは「ハーイ、ケン」というレスポンスが返り、仲間として受け入れられます。「アル中のケン」は内面性としての「わたし」ではなく、外面性としての「わたし」です。
「わたし」を外面化することで、セルヘルプグループとしてのコミュニティが成立します。コミュニティが成立するとき、マクロコスモスとの連続性が確保されます。マクロコスモスとの連続性にあるとき、ミクロコスモスである人間は、演劇性として自己を認識することになります。それがAAのなかでの「語り」です。
演劇性とは何かというと、外から見られた自分の姿です。それは他人という人間に見られた自分の姿でもありますが、同時に、マクロコスモスから見られた自分の姿でもあるわけです。マクロコスモスから見られた自分の姿があることによって、クオリティの高い演劇性が確立されます。
もし自分の苦悩を語るだけ、あるいは自己賞賛を求めるだけでしたら、演劇性は低いものとなります。マクロコスモスに包まれ、マクロコスモスから見られることによって、演劇性はクオリティの高いものになるのです。
AAの「12のステップ」は祈りの姿勢を強調し、きわめて演劇性の高いものだといえるでしょう。しかしそのような演劇性によって、はじめて近代的自己から解放され、アディクションの呪縛から解放されるのだといえるでしょう。
AAの「12のステップ」では、冒頭に「われわれはアルコールに対し無力であり、生きていくことがどうにもならなくなったことを認めた。」という確認から入ります。アディクションに対して無力であることを認めるという自己認識から、回復プログラムは始まるのです。
ここで重要なことは、「認めた」という過去形からスタートすることです。完全なギブアップ宣言です。ここからスタートするのです。ギブアップ宣言の次には、「われわれは自分より偉大な力が、われわれを正気に戻してくれると信じるようになった。」という仲間の力とハイヤー・パワーの肯定があります。
これは、近代的自己の解体だともいえるでしょう。近代的自己は、理性や意志により世界を対象化し、再編成してきました。理性や意志を前提として近代社会は形成されてきたといえるでしょう。しかし理性や意志によるコントロールが効かないものとして、近代社会にアディクションが登場することにより、近代的知の枠組みは解体することになるといってもよいでしょう。
近代的知の枠組みが解体することによって、ハイヤー・パワーという超越的な力が出現するのです。超越的な力というと、イメージしにくいかもしれませんが、近代を除く人類史においては、超越的な力とともにあることが普遍的な形態であったのです。逆に近代という時代だけが、超越的な力を、知的に認めることができない時代であるといえるでしょう。
伝統的な社会においては、個人はそれ自体で完結した世界を構築することなく、マクロコスモスのなかのミクロコスモスとして認識されていました。個人は閉ざされたものではなく、マクロコスモスの一部を構成するものとして考えられていたのです。
近代の知の枠組みは、マクロコスモスとミクロコスモスの連続性を切断することによって成立したととらえることができます。それが理性や意志と呼ばれるものです。この近代的な知の枠組みを解体することによって、マクロコスモスとミクロコスモスは再び連続性を取り戻すことになります。
アディクションからの回復
アディクションからの回復には、「底を極める」ことが必要だとされています。「底を極める」までに至る状態を、臨床心理士の信田さよ子は、「『コントロール不能になるまでコントロールする』という逆説」と表現しています[9]。信田はアディクションをセルフコントロールという幻想に取り付かれた状態だと見ます。
これは他者も自分もそして自分の体も、自分の力で変えることができるという幻想である。それは、変わらなければ自分のコントロールが足りないからだという結論になり、意志の力の不足になる。
その端的な例が摂食障害である。彼女たちは、自分の身体を、食物や食欲をコントロールすることでコントロールしていく。食欲を抑えることで枯れ木のようにやせ細った手足を彼女たちは誇らしげに人目にさらす。それこそが自己の意志の力の勝利なのだ。食欲をコントロールできず醜くふとった世の男女を横目で見て、勝利の快感に浸る。
セルフコントロールの極地はあのような身体である。とすればアルコール依存症もセルフコントロールを果てしなく追い求めて破滅に向かうという点ではまったく同様であろう。[10]
このようにとことんまで飲む、痩せる、というアディクションをきわめることで転機が訪れる。この転換点を「底つき」という。[11]
アディクションに浸っている人たちをみていると、あたかも多すぎる選択肢をみずから一つずつ消していっているのではないかと思わされる。身をまかせればどこかに行きつくであろうとやりつづけ、そして究極にいたって生か死かという地点に達する。選ぶことの不安のない地点、それこそが彼らが彼女たちが初めて手にするどうしようもない現実なのだ。それはしかし選択というセルフコントロールを超える地点でもある。その地点をどこかで望んでいたのではないかとさえ思われるのである。[12]
この生か死かという選択の余地のないパニック状態である「底つき」が、アディクションからの回復には重要な転換点だと見られています。この底を極めることと回復との関係を、ベイトソンは、ダブルバインド[13]という概念を使って説明しています。
「底が極まる」という現象に、AAは非常に大きな価値を与えている。落ちるところまで落ちていないアル中患者は、救われる見込みが少ないとされる。ふたたびアルコールへ戻っていく人間のことを、彼らはよく「まだどん底まで落ちていない」という。(中略)しかし、一度絶望の淵を覗いたくらいでは、何も変わらないのがふつうである。「どん底」でのパニックは、事態好転のきっかけを与えるにすぎないものであって、それを引き起こすものではない。[14]
「底つき」はアディクションからの回復に欠かすことのできない重要な要素ではあるが、それは「事態好転のきっかけを与えるにすぎない」とベイトソンはいうのです。この「底つき」を、近代的自己に課せられたダブルバインドだと理解し、異なる答えを出すことが必要とされるとみているのです。
ベイトソンがいうダブルバインドは、答えの出しようのない問いを突きつけられて、その問いを超える答えを出す必要があるということです。説明がむつかしいので、ベイトソンのたとえを一つ引用しましょう。
禅の修業において、師は弟子を悟りに導くために、さまざまな手口を使う。そのなかの一つに、こういうのがある。師が弟子の頭上に棒をかざし、厳しい口調でこう言うのだ。「この棒が現実にここにあると言うのなら、これでお前を打つ。この棒が実在しないと言うのなら、お前をこれで打つ。何も言わなければ、これでお前を打つ。」分裂症の人間はたえずこの弟子と同じ状況に身を置いているという感触をわれわれは抱いている。しかし彼は「悟り」とは逆の、「混乱」の方向へと導かれる。禅の修業僧なら、師から棒を奪い取るという策にも出られるだろう。[15]
この禅の師は、どちらに答えても「打つ」という問いを出すわけです。そのダブルバインドに対する答えは「師から棒を奪い取る」ということでもあるわけです。答えることができなければ、「分裂症」からの回復を期待することはできませんが、高次の答えを出すことができるのならば、禅でいうところの「悟り」の段階に達することができるわけです。
最後に、「どん底」の体験とダブルバインドの体験との複雑な関係について触れておきたい。ビル・Wは、1939年に医師ウィリアム・D・シルクワースから、おまえのアル中はもう直らないと宣告され、そこで「絶望の底」を味わったと書き記している。これはAAの歴史の第一ページとされる出来事である。それについてビル・Wがどう述べているか引用しよう。「〔シルクワース氏は〕われわれアル中患者の強靭な自我に穴を穿つ武器を与えてくれた。われわれの陥った病を描写する彼の言葉には、大きな破壊力が秘められていた。われわれの肉体のアレルギーが狂気と死へわれわれを追いやっている一方で、われわれの精神の強迫観念が飲酒へとわれわれを駆り立てていることを彼は宣告したのである。」ここで医者は、「心」と「体」を分離する患者のエピステモロジー〔認識論〕の上に、強力なダブル・バインドを仕掛けている。この言葉は、患者を繰り返しジレンマに突き返すものだ。もはや自分の意志では何も解決できない―――深く無意識なエピステモロジーが変化するという「霊的経験」を通して、医者の破滅宣告が無効になるのを待つしかない―――という状況に。[16]
ここで仕掛けられたダブルバインドは、「おまえはアルコール依存だ」という宣告と、「もう治らない」という宣告です。
つまり「おまえはアルコール依存だから飲み続けるしかない」というバインドがかけられ、「アルコール依存は治しようがないので死ぬしかない」というバインドがかけられるわけです。ビルがこのダブルバインドを解くためには、アルコール依存を治すのではなく、『霊的経験』を通して世界観を変える必要があったわけです。
AAは、このビルの『霊的経験』を歴史の第一ページとします。ダブルバインドを「治療」で解くのではなく、『霊的経験』を通して、新しいコミュニティを形成するという高次な答えで解いていくのです。その高次の解決が、アディクションという意志の病を解くことになるのです。
【参考文献】
グレゴリー・ベイトソン(佐藤良明訳)『精神の生態学』1972=2000年、新思索社
脚注
[1] イヴァン・イリイチ(1926 - 2002年)は、オーストリア、ウィーン生まれの哲学者、社会評論家、文明批評家である。現代産業社会批判で知られる。著書に『シャドー・ワーク』『ジェンダー』『脱学校の社会』などがある。
[2] ギリシア神話で、宇宙開闢のとき真っ先に生じた「原初の巨大な空隙」のこと。
[4] 同前163ページ。
[5] 同前163‐164ページ。
[6] ロイ・アッセンハイマー──メリノール宣教会司祭。1938年アメリカ合衆国ペンジルバニア生まれ。1965年来日。布教活動を行う傍ら、1975年札幌市と帯広市でアルコール依存症者の回復施設・「メリノール・アルコール・センター」を開設。1985年にダルク開設を支援。近藤氏とともに薬物依存症者の回復支援に尽力。2000年アパリ初代理事長に就任。2005年脳出血で死去。
[7] 同前164‐165ページ。
[8] 同前169‐170ページ。
[10] 同前59ページ。
[11] 同前60ページ。
[12] 同前60ページ。
[13] ベイトソンを中心とする研究班が、1956年に発表した分裂病の病因と治療に関する学習理論。(1)ある抜き差しならない関係(典型的には母子)において、(2)第一次の禁止命令(例:「これこれをするな」)と、(3)それと矛盾する、メタレベルの禁止命令(例:「何をしたら怒られるかといちいち考えるな」)の並存が、(4)そのコミュニケーション・パターンの特徴として繰り返し現われるとき、関係の一方に身を置くものが、分裂病的行動を身につけるというもの。したがって、その治療も、創造的・建設的なダブル・バインドの中で遂行されなくてはならないとされる。分裂病の単位を個人ではなく関係(家族のエコロジー)であるとする点と、ユーモアや芸術などを含めて、複数のコンテクストが絡む現象一般を取り込む広さを持っている点、これは単に分裂病の理論というより、そのような問題へ接するさいに必要な、認識論的転換の提唱というべきであろう。(見田宗介、栗原彬、田中義久(編)『社会学事典』弘文堂、1994)
[15] 同前296ページ。
[16] 同前447ページ。
アディクションとコミュニティ⑴
アディクションとは
アディクションaddictionとは、日本語では嗜癖といわれるものです。嗜癖とは、一般的な辞書では「あるものを特に好きこのむ癖」と説明されますが、もう少し厳密にいうと、ある対象(物質、もの、人、行為)に対して「のめり込む」、または「はまる」こと、加えてその「のめり込む」をコントロールできなくなることです。つまり、コントロール不全のために、「好き」「好む」の程度や、その結果としての行為が、常識を逸脱した状態のことをいいます。
アディクションは、以下のように分類されています
- 物質への依存(ニコチン依存症、摂食障害、薬物依存症、アルコール依存症など)、
- 過程への依存(ギャンブル依存症、インターネット依存症、借金依存症など)、
- 人間関係・関係への依存(共依存、恋愛依存症など)、
アディクションは現代の社会構造や家族形態が生み出した病理で、本人の意志では克服することのできない病だとされています。ところがアディクションを病だと捉える見方は、医療関係者も含めて、いまだに一般知識として共有されているとは言いがたい状況にあります。
アディクションが病だと認知されるのは、多くの場合、家庭生活や社会生活の破綻という現実に追い込まれてからです。しかし、そのように病だと認知された場合でも、病因を本人の個人的資質に求める場合が少なくありません。
アルコール依存症の問題を、サイバネティックス[1]の立場から解明しようとした生態学者のグレゴリー・ベイトソンは、アルコール依存症に対する世間の見方を次のように述べています。
アルコール依存症の“原因”または“理由”を、アルコールが入っていないときの患者の生活の中に探るべきであるとする考えが、一般の風潮としてある。あの人は───醒めた状態で───“未熟である”“マザコンである”“口愛的である”“同性愛的である”“受動‐攻撃的である”“成功への不安にとりつかれている”“神経過敏である”“プライドが高すぎる”“つきあいが良すぎる”あるいは単に“弱い”、だから酒に溺れた、という言いかたがされる。[2]
これは「“自己”なるもののサイバネティックス───アルコール依存症の理論」(1971年)という論文中で述べられたものですが、この文中のアルコール依存症をアディクションに置き換えるなら、アディクションの現状に対する、一般の見方だということができるでしょう。つまり患者本人の資質の中に病因があるとする見方です。
この講義では、アディクションの病因を個人の資質に帰すような見解を採ることはありません。そうではなく、アディクションは近代社会にセットされた罠であり、その罠を生み出す母体となったのは、近代家族という家族形態であったという視点に立って、アディクションという病理にアプローチしたいと思います。
前述したアディクションの分類に含まれる項目の多くは、本来社会的な価値を有するか、社会的に賞賛を浴びる行為とされるもので形成されています。
たとえば煙草は南北アメリカ大陸を原産とするものですが、インディアンにとって「パイプでタバコを吸う」という行為は、パイプから天上へ立ち昇る煙を通じて「大いなる神秘」と通信し、会話するということを意味していました。ですからパイプは、インディアンの社会の中で、ありとあらゆる決めごとや物事の節目に用いられるものでした。儀式の前にはパイプを天に捧げもって誓いを立て、また和平交渉や取引の際にはこの聖なるパイプが回し飲みされるのです。
天上の「大いなる神秘」とパイプを通じて誓いを立てるわけですから、このときに交わした約束を破ることは絶対に許されないことでした。インディアンたちにとってのパイプは、白人にとっての聖書と同じ意味合いを持っており、インディアンのメディスンマン(呪い師)は必ずパイプを携行しています。パイプは異部族間のパスポートであり、それ自身が和平のしるしだったのです。
ですから喫煙は、本来は天上の「大いなる神秘」と通信し、和平交渉に用いられるという社会的価値を有していたものですが、現代ではアディクションとして扱われます。
もうひとつ例を挙げると、共依存(Co-Dependency)があります。共依存とは、共働で依存しあっている、あるいは従属しあっている関係性をあらわす言葉で、「依存症者の脅しに屈する」「トラブルを肩代わりする」「依存症者の感情を刺激する」「問題を隠す」などという行動により、アディクションを手助けする人たちのことをいいます。つまりアディクションの被害を受けている人たちも、無意識のうちにアディクションを手助けする役割を果たしてしまっているのだということです。それが共依存です。この共依存の関係性は、親しい友人や恋人、情愛に満ちた家族によくみられる関係性です。
友人や恋人、家族を守る上記のような行動やふるまいは、その多くが、かつては社会的に賞賛を浴びる美談とみなされていました。ところが、そのような行動やふるまいが、逆にアディクションを助長する共依存であることが明らかになってきました。かつての美談が、現在では逆にアディクションを助長するだけのものに変わってしまったのです。
アディクションに共通するものは、コミュニティを維持するのに必要とされる、一時的な酩酊状態や競争による興奮状態を招き寄せるものだということができます。つまり本来コミュニティに必要とされた賞賛を浴びるべき行為の多くが、現代社会ではアディクションとされるようになっているということです。
コミュニティに必要とされた行為がアディクションに変換されたとするならば、同じ行為のもたらすものが、個人がコミュニティとのつながりを保っている間は賞賛されるべきものであり、個人がコミュニティとのつながりを喪失した場合には、アディクションとして否定されるということになります。そうすると、ある行為が賞賛されるべき行為であるのかアディクションになるのかという分かれ道には、個人とコミュニティとのかかわりが重要な位置を占めているのだということになります。
アディクションの基となる行為が、コミュニティとつながることによって賞賛され、コミュニティとのつながりを失うことによって否定されるのならば、再びコミュニティとのつながりを見つけ出すことによって、アディクションから解放されるのだということができるでしょう。
ところが、アディクションの病因を個人の資質に求め、アディクションからの解放を個人の意志力に求めるのなら、アディクションから解放されることはないといえるでしょう。アディクションが、個人がコミュニティとのつながりを喪失した場合に発生するものならば、コミュニティへの参加を抜きにして、アディクションの呪縛からの解放はないということになります。
それならばコミュニティと個人とのかかわりを、どう理解し、どのように再構築するかという方向性を探ることができるでしょうか。このことを二回の講義を通して考えてみたいと思います。
「自己」なるもの
ベイトソンは、アディクションに苦しむ人の〈酔っている〉状態にエラーがあるのではなく、むしろ〈醒めている〉状態のほうにエラーがあるのであり、〈酔い〉はそのエラーを矯正するものだとします。
彼の〈醒め〉のありかたが、飲酒へと彼を追いやるのだとしたら、その〈醒め〉には、なにかしらのエラー(「病」と呼んでもいい)が含まれるはずだ。そのエラーを〈酔い〉が、少なくとも主観的な意味で「修正」しているはずである。つまり間違っているのは彼の〈醒め〉の方であり、〈酔い〉の方は、ある意味で“正しい”ということになる。[3]
つまりアディクションに苦しむ人が、繰り返しアディクションに陥るのは、醒めている状態のほうに何らかのエラーが含まれているということです。そのエラーを修正するためにアディクションを繰り返すわけですから、少なくとも本人にとっては、アディクションの状態のほうが「ある意味で“正しい”」のだということになります。
それでは、醒めた状態のどこにエラーがあるのでしょうか。ベイトソンは、アディクションを克服しようとする意志力にこそ問題があるのだとします。
依存症の人間をかかえた家族や友人は、「もっと強くなれ」「酒の誘惑に打ち勝て」と叱咤する。これらの言葉が、現実に何を意味するのかは定かでないが、重要なのは、依存者自身が───醒めているあいだは───自分の「弱さ」にこそ「問題」があるのだと、一般に考えている点である。彼は「わが魂の指令官」になれると、少なくともそれがあるべき姿だと信じている。しかし、「最初の一杯」のあとはもう、飲酒を止める動機が完全に消滅してしまうということは、アルコール依存症の常識だ。意識レベルで彼の「自己」は(典型的には)、「ジョン・バーリィコーン」〔アルコールの人格化〕との泥沼の戦いに巻き込まれているのである。(中略)〈醒め〉のみを指揮し、しかも裏切られてばかりいる───これがどうも「指令官」の実の姿であるらしい。[4]
醒めた状態では、本人も自分の意志をコントロールできると信じています。しかし「最初の一杯」で、意志はコントロール不能に陥ります。そうであるならば、自分で自分の意志をコントロールできるという、醒めた状態の認識に、エラーが含まれているということになるのです。
彼らが認めようとしない、あるいは認めることができないのは、酔っていようが醒めていようが、アルコール依存者の自己の全体が、「アル中パーソナリティ」なのであり、そういう自己が、アル中と「戦う」などということは、それ自体矛盾なのだという点である。[5]
ここでエラーの理由が明かされます。それは「自己」のとらえかたです。ベイトソンは「アルコール依存者の自己の全体が、〈アル中パーソナリティ〉」なのだととらえます。この〈アル中パーソナリティ〉をベイトソンは、コントロールを失い暴走する車にたとえます。
「底を極めた」アルコール依存者のパニックは、自分がコントロールしていたと思っていた乗り物が、暴走を始めたことを知った人間のパニックである。「ブレーキ」だと思っていたものを踏むと、車はさらにスピードを増す。そのとき人は、「自分プラス車」という、どう見ても自分より大きなシステムの存在を、パニックとともに知るのである。[6]
この暴走する車が「自己の全体」なのです。この「自己の全体」に含まれる一部分である「自己」が、「自己の全体」に向かって戦いを挑むこと自体が矛盾する行為だといっているのです。エラーは、この「自己」と「自己の全体」を分ける考え方にあります。ベイトソンは、「自己」と「自己の全体」を分けることはできないことを、さまざまなたとえ話で説明します。
きこりが、斧で木を切っている場面を考えよう。斧のそれぞれの一打ちは、前回斧が木につけた切り目によって制御されている。このプロセスの自己修正性(精神性)は、木―目―脳―筋―斧―打―木のシステム全体によってもたらされる。このトータルなシステムこそが、内在的な精神の特性を持つのである。
正確には、次のように表記しなくてはならない。[木にある差異群]―[網膜に生じる差異群]―[脳内の差異群]―[筋肉の差異群]―[斧の動きの差異群]―[木に生じる差異群]……。サーキット[7]を巡り伝わっていくのは、差異の変換体の群れである。その差異のひとつひとつが「観念」───情報のユニット[8]───であるわけだ。
ところが西洋の人間は一般に、木が倒されるシークェンス[9]を、このようなものとは見ず、「自分が木を切った」と考える。そればかりか、“自己”という独立した行為者があって、それが独立した“対象”に、独立した“目的”を持った行為をなすのだと信じさえする。[10]
西洋的思考のひとつにデカルト的二元論[11]というものがあり、物質的自然の領域と心(あるいはたましい)の経験に関する領域は全く無関係なものとして区別されます。きこりがその立場にたつと、斧で木を切っている場面を、「自分が木を切った」と表現することになります。
ところがベイトソンは、そのような独立した「自己」などありえないとするのです。きこりは斧を振り下ろすかもしれませんが、その斧が振り下ろされる先は、「前回斧が木につけた切り目によって制御されている」のです。つまり自己が対象になんらかの作用を加えると同時に、自己も対象によってコントロールされているということです。そのような相互作用の連続する全体として「自己の全体」が存在するということです。
デカルト的二元論による「自己」のあやうさを、ベイトソンは盲人の杖というたとえで説明します。
「自己はどこにあるか」「その境界はどこか」と誰に尋ねても、一様に混乱した答えがきっと返ってくるはずである。あるいは、杖に導かれて歩く盲人を考えても面白い。その人の自己は、どこから始まるのか。杖の先か、柄と皮膚の境か、どこかその中間か。こんな問いは、土台ナンセンスである。この杖は差異が変換されながら伝わってゆく経路の一部分にすぎない。それを横切る境界線は、盲人の動きを決定するシステム全体のサーキットを切断してしまうものだ。[12]
「杖に導かれて歩く盲人」にとっての自己なるものの境界線は、どこに引くことができるのかということです。「杖に導かれて歩く盲人」という全体として自己を把握するのでなければ、どこで線を引こうとも、自己というシステム全体のサーキットを切断することになってしまうのです。
アルコール依存者にとっての「酒との戦い」も同じです。「アルコール依存者の自己の全体」に飲酒という行為が含まれますので、飲酒だけを「自己の全体」から切り離すことはできないのです。
帰謬法による証明
ベイトソンが主張するのは、精神と物体を分かつ二元論にエラーがあるのであり、アディクションはそのエラーを正すための帰謬法(きびゅうほう)的な証明であるということです。帰謬法は背理法(はいりほう)とも呼ばれ、ある命題が真であることを証明するため、その命題の「結論が偽である」と仮定して推論を進め、矛盾が導かれることを示す方法です。
精神と物体を分かつ二元論的思考のエラーを証明し、なぜアディクションが繰り返されるのかというメカニズムを解明するために、ベイトソンは、前言語的なレベルでの意思伝達方法から、問題を解いていきます。
夢のなかでも、動物の相互作用でもそうだが、前言語的レベルでは、それ自身の否定を含む命題(「オレはオマエを噛まない」、「オレはアイツを怖れない」)をストレートに得ることはできない。否定命題を獲得するには、まず「そうでない」とされる肯定形の命題を心に思い浮かべ、あるいは実演してみて、そのうえで、それが理に叶わないことを示していくほかはない。二匹の哺乳動物が「オレはオマエを噛まない」という意思伝達を行なう方法は、試験的な戦闘を―――「戦闘ごっこ」とも呼ばれる、ひとつの「戦闘でないもの」を―――実際やってみることなのである。友好的な挨拶の多くが、“戦闘”的行為から進化してきたことの理由は、そこにある。[13]
前言語的なレベルにおいて「噛まない」ことを証明するためには、まず「噛む」ことが必要とされます。その上で「本気じゃない」ことがわかると、「噛む」ことが「戦闘」を意味する行為ではなく、「友好的な挨拶」を意味するものに変化するわけです。
この前言語的な「戦闘ごっこ」は、ベイトソンが1969年に発表した「本能とは何か」という論文の内容を簡略にまとめたものです。ベイトソンのいう帰謬法をよりよく理解するために、その一部を引用します。論文では親子の会話という形で記述されています。Fが父親で、Dが娘です。
F 噛まないことを、どうやってしぐさで伝えるか。それは、噛まないんだ。「噛まないことをする」のさ。
D でも、他にだって、していないことはたくさんあるでしょう?寝ることも、食べることも、走ることもしてないかもしれないじゃない。「噛むことはしない」と言うときにはどうするの?
F なにかしらの方法で、「噛む」ということを話題に持ち出さなくてはならない。
D はじめに牙をむくしぐさをして、それで噛まないとか?
F そういうことだね。
D でもそれだと二匹の動物が、お互いに「噛まない」って言い合うときは、両方が牙をむくことになるでしょう?
F そうだね。
D だったら、誤解して、ほんとのケンカになってしまわない?
F そういうこともあるだろうね。自分の動作に対立観念が現われているのに、当の本人が自分のやっていることを認識していないんだったら、そういう危険がいつもついてまわる。
D 牙をむいた動物は、それが「噛まない」ということを相手に伝えるためだって、自分でわかるんじゃないかしら……
F それは疑わしいな。ともかく、相手がどういうつもりでいるかということは、わかりようがない。夢だって、今見ている夢がどういうふうに流れていくのか知ることはできないよ。
D 一種の実験ね。とにかくやってみるの。
F ああ。
D ケンカが必要かどうかを知るために、ケンカするの。
F ただし、それを知ることが目的でケンカするわけではない。ケンカのなかに、というか、ケンカのあとに、自分たちのあるべき関係が現われる、ということかな。そこに「ねらい」はないよ。
D じゃあ、動物たちが牙をむいている、そのときにはまだnotはでてきていないのね。
F いないと思うね。少なくとも、そういう場合がほとんどだろう。親しい友達同士なら、最初から「これは遊びだ」と知って取っくみ合いを始めることもあるかもしれんがね。
D ずいぶんわかってきたみたい。動物の行動にnotはない。なぜならnotは、人間の言葉に含まれるものだから。そしてnotがないから、否定を伝え合うには、帰謬法っていうの?―――否定されることを実演してみなくちゃならない。今の関係がケンカでないことを証明するのに、実際ケンカをしてみるとか、相手が自分を食べないことを証明するのに、食べられる体勢に入ってみるとか……
F うん。[14]
前言語的なレベルでは、噛まないという意志を伝えるには、まず噛んでみなくちゃならないということになるわけです。アディクションも同じように、アディクションの対象に向かうことにより、アディクションを否定しようとします。しかし結果は逆に出ます。アディクションが否定されるのではなく、アディクションをコントロールしようという意志のほうが否定されるのです。
こう考えていくと、アルコール依存者の“プライド”〔オレはできるぞ〕の持つアイロニー[15]が見えてくる。それは、自己をテストに駆り立て、“自己制御”などけっしてうまくいかない、馬鹿げた試みであることを帰謬法によって証明する、精神機構の現われと考えられるのだ。つまり彼の“プライド”は、“It won’t work.”〔自分の力を頼みにしても、うまくいきはしない〕という命題へ当人を導くことを、その隠れた(前言語的レベルでの)目的にしている。この命題は、単純否定を含むものだから、一次過程〔前言語的レベル〕の内部で表現することはできない。まず実際に、ボトルを手にするところから始めるほかはない。彼は想像上の他者である「ボトル」と勇壮な戦いを開始し、それがいつのまにか「友愛の接吻」になっていることを知るのである。[16]
帰謬法の命題は、「オレはできるぞ」ではなく、「自分の力を頼みにしても、うまくいきはしない」ということだったのです。それを証明するために「自己をテスト〔飲酒〕に駆り立て」るのです。
“自己制御”のテストの結果、当人が必ず飲酒に戻っていくという事実は、この仮説を支えるものである。しかも彼が生きるのは、まわりの人が、寄ってたかって「もっとしっかりしろ、自分をコントロールしろ」という自己制御のエピステモロジー〔認識論〕を押しつけてくる環境なのだ。だとしたら、その、自己制御なるものの無効性を示すアルコール依存者の行動は、「正しい」ということにならないだろうか。依存症に陥っていること自体、世間一般のエピステモロジーの誤りを、身をもって、帰謬法的に、証明していることになるのである。[17]
アルコール依存者のまわりの人が、本人に「もっとしっかりしろ、自分をコントロールしろ」といっているのに、アルコール依存者は自分が酒に飲まれていないことを証明するために酒を飲み、酒に溺れます。このメカニズムは、自覚を促がせばアルコール依存が止まる、あるいは本人が反省すれば立ち直るという思い込みが誤りであることを証明するものです。
アディクションとされる行為は、ダブルバインドだということがいえるでしょう。小さな子どもたちが仲間と遊ぶとき、ケンカになることがよくあります。そうしたケンカの繰り返しの中で、子どもたちは仲良くなるのです。それは前言語的レベルでの意思伝達と同じです。噛むことによって噛まないことを伝達するのです。その子ども仲間の関係性は、近代以前のコミュニティにおける人間関係と同じだとみてよいでしょう。
近代以前のコミュニティにおいては、噛むことによって噛まない意思を伝達しました。前々回の講義で触れた、南風原町喜屋武の喧嘩綱も同じです。噛むことによって噛まないという意思は伝達されるのです。ところが個人がコミュニティとのつながりを失うとき、噛むことは危険な行為になります。そのため噛むことは禁じられ、綱引きならば綱を引くだけの競争になります。
ところが競争だけになったとしても、人間は、前言語的レベルにあった信頼関係を忘れることはできません。むしろ、孤立感が増すにつれて信頼関係を求めるようになるでしょう。そのとき、「戦闘ごっこ」が復活します。「想像上の他者である『ボトル』と勇壮な戦いを開始し、それがいつのまにか『友愛の接吻』になっていることを知る」のです。
アディクションを生み出す近代家族
ベイトソンはアディクションの発生するメカニズムを、精神と対象を分離して考えるという、西洋的思考法に求めました。そのように、精神(心的実体)と対象(物理的実体)とを分離して考える二元論的思考法は、17世紀の西ヨーロッパで発達します。
17世紀の西ヨーロッパでは家族意識が確立され、「家族の肖像画」が大量に製作されるようになります。その家族意識の確立の時期と二元論的思考法の確立の時期は、同時期です。家族意識の確立によって、家族は地域コミュニティからの引きこもりを開始します。それはプライバシーの確立であり、「自己」の確立にもつながります。
このように地域コミュニティから隔離された家族というプライベートな空間の中で、17世紀末に、子ども期としての〈子ども〉が誕生します。かつて子どもは、マクロコスモス(大宇宙)としての異界や他界と、ミクロコスモス(小宇宙)としての人間の世界をつなぐ中間的な存在でした。ところが、子ども期としての〈子ども〉が誕生することにより、子どもは家庭の中に囲い込まれることになります。子どもが家庭に囲い込まれることにより、家族は、マクロコスモスとのつながりが絶たれたのだとみてよいでしょう。
子ども期としての〈子ども〉の誕生に引き続く18世紀には、乳児を農村に里子に出すか、あるいは孤児院に捨てるという習俗が、ブルジョワジーだけではなく、都市のすべての階級に普及するようになります。
そして18世紀末から19世紀にかけて、ロマンティック・ラヴ(恋愛)によって結婚するという習俗が、ブルジョワジーの間で広まっていきます。このロマンティック・ラヴによる結婚の流行と同時期に、女性の財産の継承権や社会的活動が大幅に制約されるようになり、男性は外で働き、女性は家庭を守るというジェンダーが確立されていきます。そのことによって女性は家庭に囲い込まれることになります。その時期に、母性愛が称揚されるようになり、女性には母性愛という〈本能〉が備わっているとみなされるようになります。この女性の家庭への囲い込みと母性愛〈神話〉の確立により、乳児を里子に出したり、孤児院に捨てるという習俗は減少していき、母親の母乳による育児が増加していきます。
そして19世紀には、子ども部屋をもうけることが普及し、19世紀後半には、子ども部屋における「子どもの世界」が誕生することになります。この「子どもの世界」の誕生により、①子ども中心主義、②ロマンティック・ラヴによる結婚、③母性愛、という近代家族の枠組みが完成することになります。
この19世紀後半に、西ヨーロッパのブルジョワジーの家庭で完成した近代家族は、20世紀をかけて民衆化し、日本をはじめとする後発地域の家族モデルとなっていきます。
このような近代家族が形成されていくプロセスは、地域コミュニティや親族ネットワークからの家族の引きこもり現象と対応するものでした。そうすると、かつての地域コミュニティや親族ネットワークにおいて、社会的価値を有し、賞賛を浴びるべきものとされた行為や行動が、アディクションへと反転することになります。
そこに近代社会にセットされた罠があります。その罠を生み出す母体となったのは、近代家族という家族形態であったといえます。
近代家族には地域コミュニティや親族ネットワークから孤立があります。近代家族が完成した19世紀後半のイギリスのヴィクトリア時代(1837‐1901年)の家族像を、イギリスの歴史学者ローレンス・ストーン[18]の『家族・性・結婚の社会史』(1977年)の記述から拾い上げてみましょう。ストーンは、近代家族において女性が社会的に孤立するようになり、存在感が空疎なものになっていったと述べています。
妻は、親族との絆が弱まったことによって、以前は夫の下での生活に順応するという困難な仕事や、子育てとか子どもの世話といった難しい仕事に際して利用することができた濃密な外的助力から引き離された。今や彼女は、夫婦喧嘩の際の味方や、深刻な性格の不一致が生じた場合の助言者を他に求めることができなくなった。子守りや教育という負担を共有してくれる親類の人々がいなくなったため、子どもたちがまだ幼いあいだの彼女の生活は、非常に孤立的で退屈なものになった。そして、子どもたちが家を出る頃には、今や彼女の存在感は非常に空疎なものになっており、社会的あるいは経済的な職務というものをなくしてしまっているのである。[19]
地域コミュニティや親族ネットワークから孤立することにより、女性にとって育児は「非常に孤立的で退屈なもの」になり、子育ての後「彼女の存在感は非常に空疎なもの」となります。そして「社会的あるいは経済的な職務」を喪失した存在になるのです。
母親の孤立感と空疎感の反動として、家族的な情愛は、「爆発的親密性」と呼ばれるほど濃厚なものになります。ストーンは、近代家族が女性と子どもの抑圧の上に成立すると述べ、近代家族の緊密で濃厚な情緒的結びつきが、「爆発的親密性」であることを指摘しています。
しかしながら、中産・下層階級にはヴィクトリア時代風の家族に固有ないくつかの特徴があった。ひとつは、歴史上最初に見られた永続的であると同時に親密でもあった家族類型であった。(中略)こうした永続性のある家族単位の中で、妻と子どもの抑圧と、その道徳的安寧に対する強烈な情緒的および宗教的関心との結びつきが発達した。妻を服従させることと、子どもの性格と自律的な心理的動因を打ち砕くことは、家族の全構成員の情緒生活の全体が、ほとんどもっぱら核家族という境界線内に集められているような状況において生じたことである。こうした家族類型の心理力学(サイコ・ダイナミックス)は、適切にも「爆発的親密性(explosive intimacy)」ということばで言い表わされてきた。[20]
孤立感と空疎感に包まれた中での「爆発的親密性」は、アディクションを生み出す母体になるといってもよいでしょう。
「爆発的親密性」の中においては、「戦闘ごっこ」は封印されます。「戦闘ごっこ」が「ケンカのあとに、自分たちのあるべき関係が現われる」ためになされるとするならば、「爆発的親密性」の中における、リアルな「自分たちのあるべき関係」が現われてはならないのです。前々回の講義「母性愛という神話(2)」で触れたように、子どもは母親の真意を理解してはならないのです。その真意は、家庭に囲い込まれた状況での子育てによる、母親の孤立感と空疎感であるからにほかならないからです。
【参考文献】
ローレンス・ストーン(北本正章訳)『家族・性・結婚の社会史』1977=1991年、勁草書房
グレゴリー・ベイトソン(佐藤良明訳)『精神の生態学』1972=2000年、新思索社
脚注
[1] 生物と機械における制御と通信を統一的に認識し、研究する理論の体系。ネガティヴ・フィードバックによる恒常性維持のシステム。社会学者の勝又正直は、エアコンを例にしてサイバネティックスの概念を説明している。たとえば室温24度に設定したエアコンは、設定温度からのずれがあるとそれを打ち消すような働きをすることによって、室温を一定の状態に保つ。このような変化(ずれ)を打ち消すような働きで、しかもその結果が自分に戻ってくるような働きのことを、ネガティヴ・フィードバックという。このようにネガティヴ・フィードバックをつかって自己の安定を維持するようなシステム(まとまり)をサイバネティクス・システムという。この際、重要なのは、相互関係によって形成されるシステムは、この場合、エアコンではなくて、エアコンが置かれた部屋全体がシステムだということだ。
[3] 同前423ページ。
[4] 同前424ページ。
[5] 同前425ページ。
[6] 同前446ページ。
[7] 《巡回の意》1 電気回路。回路。2 自動車・オートバイなどの競走用につくられた環状道路。3 劇場・映画館などの興行系統。
[8] 全体を構成する一つ一つの要素。
[9] 連続。連続して起こる順序。
[10] 同前431ページ。
[11] デカルト(1596-1650)は、空間的広がりを持つ思考できない延長実体(いわゆる物質)と、思考することができる空間的広がりを持たない思惟実体(いわゆる心)の二つの実体があるとし、これらが互いに独立して存在しうるものとした。この考えはデカルト二元論と呼ばれ、実体二元論の代表的理論として取り扱われている
[12] 同前432ページ。
[13] 同前441‐442ページ。
[14] 同前109‐110ページ。
[15] 皮肉。逆説。反語法。
[16] 同前442ページ。
[17] 同前442ページ。
[18] ローレンス・ストーン(Lawrence Stone、1919 -1999年)は、イギリスの歴史学者。イギリス近代史、とくに17世紀のイングランド内戦や家族史で知られる。著書として『イギリス革命の原因』『貴族の危機』『大学史』『離婚の社会史』などがある。
[19] ストーン『家族・性・結婚の社会史』581-582ページ。
[20] ストーン前掲書577-578ページ。
ヘアーインディアンと家族
- 1. さまざまな家族が語られ始めた
- 2. ヘアー・インディアン
- 3. 世帯という概念の成立しない社会
- 4. 個人を中心とした社会
- 5. 流動的な夫婦関係
- 6. 流動的な親子関係
- 7. 父親は社会的な父親
- 8. ミウチ
- 9. まとめに
1. さまざまな家族が語られ始めた
共時的に家族は、多様化いていることが指摘されてきました。未婚独身、結婚しない異性との同棲、子どもをもたない夫婦、ひとり親家族、離婚独身、ステップ・ファミリー、共働き家族、伝統的核家族、単婚にこだわらない夫婦(合意による婚外の性関係)、別居家族、同性同士のカップル、友人コミュニティ、伝統的三世代同居、二世帯型同居、高齢者独居(寡婦・寡夫)、一夫一婦婚、一夫多妻婚、一妻多夫婚、結婚をしない家族、ペットを含む家族などというように。
(共時的:言語学者ソシュールの用語。時間の流れや歴史的な変化を考慮せず、一定時期における現象・構造について記述するさま)
現在の家族社会学の研究では、家族を定義するのはむつかしいとされています。それは「家族なるもの(The Family)」の意味するものが、通時的には異なった内容を意味するものであり、共時的には多種多様な形態をとるものであるからです。
(通時的:言語学者ソシュールの用語。関連する複数の現象や体系を、時間の流れや歴史的な変化にそって記述するさま)
ヨーロッパにおいてThe Familyは、通時的にいうと、長い間、一人の家父長の下で生活を共にする、親子や血縁者、使用人や徒弟などの非血縁者までも含む言葉として使用されていました。17世紀から18世紀にかけて、The Familyという言葉の意味するものが、見返りを求めない情緒と私的な事柄(プライバシー)という新たに登場した意味と結びつき、親子関係からなる核家族を意味するものに変化していきます。
家族を定義するのはむつかしいのですが、家族は「現実の家庭環境がどうであれ、すべての人間は『家族的存在』であるほかはない」(斎藤環『家族の痕跡』)存在であるともいえます。
そこで今回の講義では、さまざまな家族が語られてきたことを受けて、原ひろ子著『ヘヤー・インディアンとその世界』(1989年、平凡社)を主軸にして、家族を考えてみたいと思います。
2. ヘアー・インディアン
ヘヤー・インディアンとはカナダの北極圏に先住し、インディアン中で最北部に住む部族です。人口は300人から500人(1960年代当時)で、約9万平方キロ(日本の本州の四分の一弱)の地域に住み、少グループに分かれて分散してキャンプし、食料を求めて常にテントの移動を余儀なくされています。
主な食料は野ウサギで、そこからヘヤーhare(野ウサギ)という名称がついています。(現在はカナダ政府の同化政策によって伝統的な生活は消滅しつつあると言われています)

広大な極北圏で猟をするヘヤー・インディアンは、定住することなく一年のほとんどをテント小屋で暮らします。ところがテント小屋のメンバーは流動的で一定することはありません。そのような流動的なテント・メンバーの生活の中で重視されるのが、インセスト・タブーです。子どもが生まれると、必ず誰が父親であるのかが決定されます。そのことによって、インセスト・タブーとされる人間関係が決定されるのです。このインセスト・タブーを守ることによって、ヘヤー・インディアンのコミュニティは成立します。
ヘヤー・インディアンは徹底して個人主義的であり、男女のカップルは、あくまでも気の会うものどうしのカップルであり、育児は楽しみの一つとされ、生物学的な母親にということではなく、育てることのできる者が子どもを育てるということが基本の社会です。
現在の資本主義経済における先進諸国の家族は、欧米諸国でここ30年(1980‐2008年)ほどで婚外子割合が急増するなど、劇的な変化を遂げつつあります。
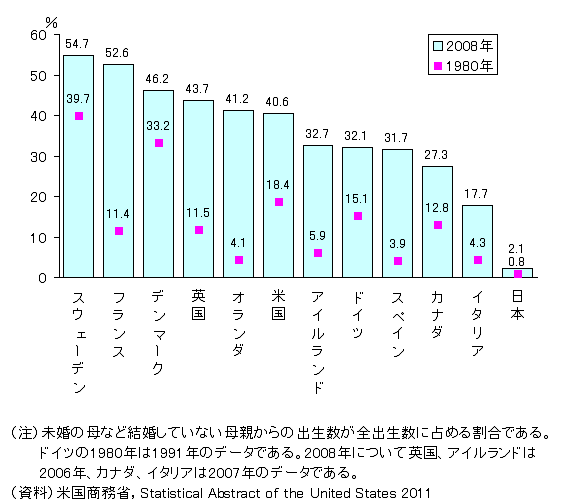
それは、結婚制度による結婚よりも、カップルでいることを重視する社会に変化しつつあることを意味するのだといえるでしょう。
このように結婚制度によらない、気の合った者どうしがカップルをつくるという社会が、「未開」と呼ばれる社会にもありました。それは文化人類学者の原ひろ子(1934‐2019)が、1961年から63年にかけてフィールド・ワークした、ヘヤー・インディアンの社会です。
3. 世帯という概念の成立しない社会
そこで彼女が発見したのは、メンバーの固定した「ある程度持続的に、寝食を共にする生活集団」としての「家族」ではなく、個人を中心としたネットワーク社会でした。ヘヤー・インディアンは丸木小屋やテントで生活しますが、そのメンバーは一定することなく、流動的であり、そこには「世帯」という概念に当てはまるものはなかったのです。
丸木小屋の持ち主は、AとかQとか特定の個人だ。そして、そこをまあまあ常時利用している核になるような人びとも、だいたい決まっているのだが、すべての丸木小屋に関して、誰がいつどこに寝ているかということは、一晩単位で変動するのだということがわかってきた。特定のテントに寝る人びとが誰と誰であるかはじつに流動的なのだ。(原ひろ子『ヘヤー・インディアンとその世界』207‐208ページ)
そこで原は、世帯という概念を捨て、テントで生活を共にする一時的な居住集団を「テント仲間」と呼ぶことにします。そして、家族に当たるものを「ミウチ」とし、性生活の相手を「ツレアイ」とし、個人のパーソナリティ要因を契機とする親族ネットワークを「シンルイ」と名づけて、ヘヤー社会の人間関係を分類しました。

4. 個人を中心とした社会
ヘヤー・インディアンの社会は、徹底して個人主義的な社会であり、個人のパーソナリティを重視してネットワークが形成される社会でした。そのため集団を統合するような指揮系統が発達することは少なく、その代わりに流動的なネットワークが社会を維持するものとして機能することになります。
宗教的にはコミュニティを統合するような宗教はなく、各個人にその個人特有の守護霊があり、守護霊と個人の結びつきが、もっとも重視されます。各個人はそれぞれが守護霊を持っており、その守護霊が個人の行動を決定します。ですから徹底して個人のパーソナリティが重視されるのです。
ヘヤー・インディアンは、一人ひとりが自分の守護霊をもっている。それはビーヴァーやテンやクズリなどの動物で、一人につき一種の動物が守護霊となる。三歳ぐらいの子どもでも、「僕ね。昨夜の夢にテンが出てきて、今日はブッシュに入ってはいけないと言われたんだよ」などと口走る。すると、まわりの大人や年上の子どもたちが、「そうか、そのテンがお前をずっと守ってくれるんだよ」と決めつける。こうして順調にいけば、三、四歳以上の子どもたちがいつの間にか夢の啓示を得て、どの動物が自分の守護霊であるのかを知るのである。(同前341ページ)
ヘヤー・インディアンの社会では、一般論は成立しません。すべて守護霊と個人との霊的な交信によって決定されるからです。ですから「一人ひとりの子どもたちを独自の人格と特徴をもった個人」として見られることになります。
他者から教わるという概念も成立しません。自分で観察し、試行し、自分で修正することによって、「○○をおぼえる」ことになるのです。
テント仲間のメンバーが常に変化するのだから、特定の「家庭料理」とか、「この家庭のやり方、流儀」、「家風」というものも存在しない。技術や習慣なども、すべて個人個人のものなのである。(中略)そして、一人ひとりの人間が、「その人らしさ」をもった個人として充分に充実して生活しているのである。(同前244‐245ページ)
このように他者を一般論で見ることをせずに、個別性で見るという見方は、ネットワーク社会といわれる現代社会に通じるものがあるといえるでしょう。
5. 流動的な夫婦関係
ヘヤー・インディアンは「家族は同じ屋根の下で住むのが当然だ」という考え方が弱く、男女のカップル関係も流動的です。
テント仲間を構成する男女の対は、(中略)労働力のバランスのとれたパートナーで、気が合えばよいのだ。セックスもするけれど、相手に惚れ込んでいるかどうかということは、別の次元に属することなのだ。男も女も、個人差はあるが、一時に一人ないし七、八人の恋人をもっている。(中略)一般には、恋と日常生活は別のものである。(同前223ページ)
「男女の同棲は、あくまでも気の合っている間だけつづければいい」という気持ちが流れていることだ。したがって、「偕老同穴の契りを結ぶ」というような考え方はいっさい存在しない。(中略)つまり、西欧の近代的な夫婦の理念にみられる「二人の男女が愛情を深め合って長い年月を共に送る」ということは、ヘヤー・インディアンの男女の生活においては二義的なものなのである。(同前242ページ)
偕老同穴:夫婦が仲むつまじく添い遂げること。夫婦の契りがかたく仲むつまじいたとえ。夫婦がともにむつまじく年を重ね、死後は同じ墓に葬られる意から。▽「偕」はともにの意。「穴」は墓の穴の意。
6. 流動的な親子関係
ヘヤー・インディアンの社会は、個人を中心としたネットワーク社会なので、生みの母が子どもを育てなければならないという概念は存在しません。
「乳児は、その子を生んだ母親が育てなければならない」という我われ近代日本人の理念における大前提が、この社会には存在しない。「子どもは、育てられる者が育てればいい」のであって、「それが実の母親なら望ましいが、何も実の母に限ることはない」という考え方である。ヘヤー社会にはじつに養子や里子が多い。聞いてみると、「生まれてすぐは、父方の祖母に育てられて、隣りのテントのシンルイではない小母さんから乳をもらい、それから母の妹の所で暮して、七つのころ、一時、母親と暮したけれど、あとは母の兄の家族と暮して、今の夫と結婚した」というような話がよくある。このような西洋や日本でなら「家なき子」として悲劇の主人公になりうるようなケースが、彼らの間では決して悲劇とは考えられていないのである。(同前242‐243ページ)
ヘヤー・インディアンの社会では、育児は「遊び」と同じくらい「楽しいこと」のカテゴリーに入り、養子や里子の引き取り手に困ることはありません。「育児上の用事は、ほとんど子どもの母親そのほかの女の手によって行なわれるが、父親や男たちも、気軽に哺乳壜にミルクを調合したり、おむつを替えたり、遊んでやったりする」ということになるのです。
7. 父親は社会的な父親
人間関係、親子関係の流動的なヘヤー社会でも必ず決定しなければならないことがあります。それは誰が子どもの父親であるかということです。
彼らは、誰と誰がいつ、どこで、一緒にキャンプしていたかということに強い関心をもっている。そして、男女の性交によって妊娠し、人間の妊娠期間が280日ぐらいだということも知っている。だから、出産日から逆算して「この子の父親は、あいつだ」ということを推定し、さらに世論としての噂話や、産婦の話から、その子の父が決まることになる。(同前256ページ)
ヘヤー・インディアンは、生物学的な父親を確認しようとする必要は感じない。これに対して、社会的な父親が決まることは、母親にとっても、またヘヤー社会全体にとっても、絶対不可欠な事柄なのである。(同前257ページ)
この引用で重要な点は、父親の確定が「世論としての噂話や、産婦の話から」なされるということです。ある程度は生物学的な父親を推定するのですが、「生物学的な父親を確認しようとする必要は感じない」というのです。それでは何のために父親の確定が必要なのかというと、インセスト・タブーの範囲を確定するためです。そのため社会的な父親が決まることは、「絶対不可欠な事柄」ということになるのです。
インセスト・タブー
インセスト・タブー (Incest Taboo)とは、人間社会において、特定のカテゴリーに該当する親族との結婚や性的関係を禁じる社会的規範のことで、あらゆる社会で普遍的にみられる。
インセストは、近親婚や近親相姦と訳される。またタブーは、禁忌と訳されるように、たんに禁止というのではなく、その社会の成員すべてが規範をおかすことに強い怖れや忌(いみ)の感情をいだき、順守することが当然とうけとめているものである。
人間以外の霊長類やその他の生物種にも、母子間や兄弟・姉妹間の性行為をさける事実があることはよく知られている。しかし、こうした動物のインセストの回避とインセスト・タブーは、現在では区別してあつかわれている。それは、人間の場合にはタブーの対象となっているインセストの概念そのものが、それぞれの社会、歴史、文化によってかなりことなり、近親にかぎらず疑似的な血縁関係もふくまれるなど、恣意的(しいてき)につくられたカテゴリーといえるからである。
母と息子、父と娘、兄弟・姉妹同士の性的関係は、ほとんどの社会で禁じられており、実際には血のつながっていない養子や義理の関係にも適用されている。しかし、オジ・メイ、オバ・オイ、イトコ同士となると、インセストとみなす範囲の偏差がはげしく、母方であるか父方であるか、交叉イトコ、平行イトコなどによっても違いがある。さらに、氏族(クラン)、半族といった社会組織による外婚規制にも、インセスト・タブーの概念が入りこんでいる。(『Microsoft エンカルタ百科事典 2000』より)
それでは噂話や産婦の話によって父親を決定していいのかという疑問と、もし娘が生まれた場合、生物学的な父親と性愛する可能性があるのではないのか、それはインセスト・タブーを破ることになるのではないのかという疑問が生じます。
文化人類学者のクロード・レヴィ=ストロース(1908-2009)は、その著『親族の基本構造』(1949)において、インセスト・タブーの意味することを、男性たちに互酬規則を命じるものだと捉えました。
つまりインセスト・タブーの意味するところは、たんにインセストのカテゴリーに入った女性たちとの性愛や婚姻を禁じるものではなく、インセストのカテゴリーに入った女性たちをその帰属する集団とは異なる他の男性と交換せよ(贈与交換)、という命令だとしたのです。
つまり、インセスト・タブーは禁止を意味するだけではなく、贈与交換することによって親族という仲間をつくるための規則だといえます。インセスト・タブーが贈与交換の規則であるならば、父親の意味するところは生物学的なものだけではなく、社会関係を成立させるための社会的存在であるということになるのです。
贈与交換とはマルセル・モースの『贈与論』(1923-24=1943)で論じられた概念で、贈与と返礼の交換が社会を存続させる重要な役割を担っているという理論で、レヴィ=ストロースの提唱する構造主義に大きな影響を与えました。
父親という存在がなぜこのようにややこしいのかというと、父親というのは人類にしか存在しない社会的存在であるからです。霊長類研究のサル学では、父親という存在は、ヒトが誕生したと同時に生成した社会的存在であるとします。
サル社会には、父親は存在しない。父親というのは、家族という社会的単位ができる、つまり、ヒトが誕生したと同時に生成した社会的存在である。ということは、父親は家族の成立に伴って創り出されたものであり、極言すれば発明されたものなのだ。一方、母親は生物学的存在であるとともに社会的存在だ、という二面性を持っているのである。(河合雅雄『子どもと自然』178ページ)
レヴィ=ストロースによると、インセスト・タブーによって家族やコミュニティという社会単位が誕生し、同時に人間という文化的な存在も誕生することになります。父親という存在も人間が誕生すると同時に、生成されることになるのです。インセスト・タブーを破ったならば家族もコミュニティも形成されず、人間でもなくなります。そういう社会では父親は存在しないのです。
8. ミウチ
社会的父親が決定されなければならない最大の理由は、インセスト・タブーです。インセスト・タブーの守るべき範囲を設定するために、社会的父親が決定されなければならないのです。
人間関係が流動的なヘヤー社会でも、父、母、父母をともにするキョウダイ、ツレアイ(性生活の相手)とその間の子どもに対しては、ツレアイを除いて、これらの人びとと性交渉をもってはいけないというタブーがあります。このタブーのために、社会的父親が決定されなければならないのです。父親が確定されることによって、父母をともにするキョウダイが確定することになり、同父母キョウダイは、インセスト・タブーの対象となります。つまりインセスト・タブーの範囲を確定するために、社会的父親の決定が「絶対不可欠な事柄」になるのです。
原は、このようなインセスト・タブーの範囲内にある人びとを、「ミウチ」という言葉でカテゴリー化します。
ヘヤー・インディアンの「ミウチ」は、幾重にも張り巡らされたタブーによって、運命を共にする相互関係をもつことになります。しかし、「ミウチ」のカテゴリーに該当する人びとが、「我われ意識」をもつことはないとされます。一人ひとりが個人的に、もろもろのタブーに「ミウチ」として拘束されるだけなのです。
ヘヤー・インディアンの「ミウチ」は、一つのテントで寝食を共にすることによって、生活共同体を形成しているのではない。しかし、超自然的に規定されたタブーの存在によって、運命を共にする相互関係をもつのである。(中略)しかし、ヘヤー・インディアンの考え方によると、特定個人(A)の「ミウチ」のカテゴリーに該当する人びとが、「我われAのミウチに当たる者ども云々」といった、「我われ意識」をもつことはないのである。彼らの一人ひとりがそれぞれ常に、「私はAとミウチだから」ということを意識して行動しているに過ぎない。((原ひろ子『ヘヤー・インディアンとその世界』268ページ)
ヘヤー・インディアンにおける「ミウチ」は、家族の究極の形態を示すものだといえるでしょう。「ミウチ」はインセスト・タブーとそれにともなうさまざまなタブーを共有するだけであり、そこには「我われ意識」は存在しないのです。つまり、家族の究極の姿は、インセスト・タブーを協約する関係性そのものになってしまうのです。
9. まとめに
人類は贈与交換を行なうことによって社会を形成してきました。そして女性の贈与交換を行なうことによって、親族を形成し、家族を形成してきました。この親族からコミュニティが形成されることになります。
女性の贈与交換ということの根底にあるのはインセスト・タブーです。インセスト・タブーは、精神分析における無意識のように、親族=コミュニティをつくるようにと命令する視えない構造だということができます。この視えない構造によって、家族が形成されるのだといえるでしょう。つまり、コミュニティと家族は、分離できないものとして同時に生成されたものだといえるのです。
近代家族は、家族をコミュニティから分離させることによって誕生しました。家族がコミュニティと不可分な存在であるとすると、家族にとってコミュニティとは何であるのかが、再び問われることになるでしょう。そして近代家族が個人主義的にならざるを得ないものだとすると、ヘヤー・インディアンにおける個人の守護霊に代わるものが何であるのかが、問われなければならないといえるでしょう。
【参考文献】
マルセル・モース(吉田禎吾他訳)『贈与論』(1925=2009年、ちくま学芸文庫)
レヴィ=ストロース(福井和美訳)『親族の基本構造』(2000年、青弓社)
河合雅雄『子どもと自然』(1990年、岩波新書)
斎藤環『家族の痕跡』(2010年、ちくま文庫)
原ひろ子『ヘヤー・インディアンとその世界』(1989年、平凡社)
エリコ・ロウ『太ったインディアンの警告』(2006年、NHK出版 生活人新書)
- 1. インドを目指して「発見」されたアメリカ
- 2. インド人?の住むアメリカ
- 3. ピュ-リタンの入植とインディアンの援助
- 4. インディアンから白人への土地の移転
- 5. WASP(ワスプ)
- 6. インディアンの清掃
- 7. 米軍兵士になって覚えた白人食の味
- 8. 米軍基地化と本土返還で悪化した沖縄の人々の食生活と健康

1. インドを目指して「発見」されたアメリカ
ヨーロッパは古代からインドや東南アジア地域との香辛料の交易ルートを持っていました。しかし、1453年にオスマン帝国〔トルコ人によるイスラム王朝〕がビザンツ帝国〔古代ローマ帝国の存続として残った東ローマ帝国〕を滅ぼし、地中海の制海権を得ると、これらを通る交易路に高い関税をかけました。
そのためヨーロッパ諸国は地中海を通らずにインドに行ける方法を模索することになります。その結果「発見」されたのが、アメリカという「新大陸」だったのです。

【図像説明】経済的に重要なシルクロード(赤)と香辛料貿易のルート(青)は、オスマン帝国時代に遮断される。1453年のビザンツ帝国の崩壊は、アフリカ航路開拓のための探検を促し、大航海時代を引き起こした。以下特に参照を明記していない図像はネットから借用しています。
2. インド人?の住むアメリカ
インドへ向けて西側のコースを取ったのがクリストファー・コロンブス(1451ごろ-1506、イタリアの探検家)でした。彼は1492年に「インド」に到着します。しかしそれはインドではありませんでした。
アメリゴ・ベスプッチ(1454-1512、イタリアの探検家)は1499~1500年、1501~02年の2回にわたって西側のコースで「インド」を探索し、それがインドではなく「新大陸」ではないかと提唱しました。その提唱により、「新大陸」には「アメリカ」という名称が付けられることになりました。
しかしそこに住む人たちには、「インド人」という名称がそのまま使用されたのです。スペイン語・ポルトガル語ではインディオといい、英語ではインディアンと発音されます。
もちろん「新大陸」にいたのはインド人ではありませんでした。彼らは1万2千年ほど前に、氷河期のベーリング海峡をこえて北アメリカに移住し、アメリカ先住民となったモンゴリアンだったのです。(エンカルタ2000より)

コロンブスが到着した頃の南北アメリカ大陸には9000万人を超える人々が住んでいたと推定されています。この膨大な人口のほとんどは、白人との接触により絶滅寸前まで追い込まれました。
15世紀末~16世紀、すなわちコロンブスがカリブ海に到着したころ、南北アメリカの陸地には9000万、あるいはそれ以上の人間がすんでいたと推定されている。そのうちおよそ1000万人は北アメリカ、今日のアメリカ合衆国とカナダにすみ、3000万人がメキシコ、1100万人が中央アメリカ、44万5000人がカリブ海の島々、3000万人が南アメリカのアンデス地域、900万人が南アメリカのその他の地域にすんでいた。人によっては、これよりも少ない推定をすることもある。アメリカのどこでも同じだったが、ヨーロッパ人と接触するや、戦争、飢餓、強制労働、新しい伝染病などのために、先住民の人口は激減した。(エンカルタ2000)
同時期(1500年)のヨーロッパの推計人口は5600万人とされています。つまりヨーロッパ人は、自分たちの2倍近い人口を激減させたのです。
その当時の南北アメリカ大陸には千に近い部族=民族があり、ユーラシア大陸の西端の半島に過ぎなかったヨーロッパと比較すると、独特の伝統文化を育んでいた文明地域だったのです。
西欧史では「コロンブスが1492年に発見した新大陸」とされているアメリカ大陸は、実は未開の新世界などではありませんでした。
実際にはそこで少なくとも千に近い部族、総計数千万人の先住民族が千年の昔から広い大陸の東西南北に分散、それぞれに民主的な部族社会を築き、独特の伝統文化を育んでいたのですから、人類の文明の歴史が古い大陸だったのです。(エリコ・ロウ『太ったインディアンの警告』)

インディアンを絶滅寸前まで追い詰めたヨーロッパ人にも、侵略の三つのタイプがありました。
中南米を占領したスペイン人はインディアンを労働者として使役し、キリスト教徒に改宗させようとしました。
カナダに進出したフランス人は、植民地を作ることよりも毛皮交易に熱心でしたので、インディアン虐殺の歴史は少ないものでした。
本国での宗教戦争から逃れて北米に進出したイギリス人は、インディアンを地上から抹殺し、インディアンのいなくなった土地に自分たちの信じる信仰の王国を建設しようとしました。
侵略のこの三つのタイプが、南北アメリカ大陸の歴史を変えることになります。
彼ら16世紀のスペイン人にとって、2つの目的、商業的目的と宗教的目的のためには、アメリカの先住民が必要だった。征服者は土地と先住民の労働力を手にいれようとし、キリスト教の聖職者や修道士たちは先住民の魂をほしがった。いずれも先住民には破滅的な結果しかもたらさなかった。(…)
カナダでは、いくぶん事情がことなった。この地に入ったフランス人の関心は、毛皮交易にあった。(…)彼らは先住民を自分たちと平等な人間とみなし、先住民との結婚も当然なことと考えていた。
いっぽう、イギリス人はまったく逆だった。彼らは土地をもとめたために、先住民を障害とみなしたのである。大西洋沿岸部にすみついた大勢のイギリス人は、先住民を力ずくでおいだした。こうして、今日のカナダとアメリカ合衆国とでは、ヨーロッパ人との出会い以後の先住民の歴史が大きくことなることになった。(エンカルタ2000)
3. ピュ-リタンの入植とインディアンの援助
1620年に、ピルグリムファーザーズ(Pilgrim Fathers「巡礼始祖」)と呼ばれるイギリスのピューリタンの人々が、北アメリカに植民地を築きました。これがアメリカ合衆国(以下アメリカ)建国の礎(いしずえ)となります。
ピューリタンとは、16世紀後半、英国国教会の改革政策を不徹底とし、いっそうの宗教改革をおしすすめようとしたグループ、またその流れをくむ人々のことで、「清教徒」とも訳されます。アメリカでは、ピューリタンの道徳主義と、神との契約による選民意識とが、その国民性に強い影響をおよぼしました。
彼らの入植当初の状況は厳しく、半年で半数程が病死したが、先住民インディアンのワンパノアグ族が食糧や物資を援助したおかげで冬を越えることができました。
ヨーロッパからの長い船旅の末に、「未開の地」にたどり着いた白人は、消耗しきっていました。(…)ビタミンC不足による壊血病で死にかけていた人々を、ビタミンCが豊富なクランベリーで癒し、栄養失調で痩せこけていた人々に七面鳥やトウモロコシで栄養を与え、サバイバルに必要な狩の仕方や農耕の仕方を教えたのは、異邦人を友として受け入れる友愛精神と包容力に満ちた、アメリカ・インディアンだったのです。(『太ったインディアンの警告』)
しかし間もなく、白人入植者たちは入植範囲を拡げ始め、インディアンとの間で土地と食料を巡って対立が発生し、戦闘が起きるようになりました。
ピルグリムはまず1630年にマサチューセッツ族の領土に進入。ピルグリムの白人が持ち込んだ天然痘により、天然痘に対して免疫力があまりなかったマサチューセッツ族の大半は病死しました。
天然痘(てんねんとう、 Variola、Smallpox)は天然痘ウィルスを病原体とする感染症の一つである。ヒトに対して非常に強い感染力を持ち、全身に膿疱を生ずる。致死率が平均で約20%から50%と非常に高い。仮に治癒しても瘢痕(一般的にあばたと呼ぶ)を残す。天然痘は人類史上初めてにして、唯一根絶に成功した人類に有害な感染症である(2021年現在)。
種痘(しゅとう)とは、天然痘の予防接種のことである。ワクチンをY字型の器具(二又針)に付着させて人の上腕部に刺し、傷を付けて皮内に接種する。1980年に天然痘ウイルスは撲滅され、自然界に存在しないものとされているため、1976年を境に日本では行われていない。
1636年には1人の白人がピクォート族に殺された事がきっかけでピクォート戦争が発生。ピルグリムは容疑者の引き渡しを要求しましたがピクォート族がそれに応じなかったため、ピクォート族の村を襲い、大量虐殺を行いました。
インディアンとピューリタンのあいだには乗り越えがたい文化の壁がありました。インディアンはピューリタンの苦境を救ったのですが、ピューリタンはその返礼に、インディアンの大量虐殺に向かったのです。
社会学者のマックス・ウェーバーは、ピューリタンの排他性を次のように述べています。
たとえば、とくにイギリスのピュウリタニズムの諸著書がしばしば、人間の援助や人間の友情に一切信頼をおかないよう訓戒している堅調な事実にしてもそうだ。穏健なバックスターでさえ、もっとも近しい友人に対しても深い不信感をもつことをすすめ、ベイリーはあからさまに、誰も信頼せず、迷惑のかかるようなことは誰にも言わないのがよい、神だけが信頼するかただ、と説いている。(『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』)
ウェーバーは資本主義の精神を「吝嗇(けち)の哲学」名付けていますが、アメリカ・インディアンとピューリタンとの文化的な溝の最大のものは、贈与交換と資本主義の精神との差異にあったといえます。
贈与交換とは、互いに贈り物を交換する交易形態をいうものです。贈り物を交換することによって友好関係を獲得するのです。そのような社会では、より多く贈り物をするものが社会的な威信を獲得したのです。インディアンの社会は贈与交換によって成立する社会だったので、異邦人であるピルグリムたちの苦境を救ったのです。
一方のピルグリムたちはプロテスタントでした。プロテスタントは教会に富を積むことを拒否した人たちでした。
カトリックにおいて、教会は地上における天国の入り口とされていました。聖書の教えでは地上に富を積んではならず、富は天国に積むべきだとされていました。そのため地上における天国である教会に富は積まれたのです。
その教会の腐敗を糾弾したプロテスタントは、教会に富を寄進することを止めてしまいました。
教会の権威を否定するために、ピューリタンは僧院におけるような禁欲的な生活を自らに課しました。その結果、富は教会ではなく地上(家庭や企業)に積まれることになりました。その無限に蓄積される富が、無限に富の増殖を続ける資本主義を生み出すことになるのです。
ピューリタンにとってインディアンは嘘つきの怠け者と映うつりました。インディアン社会の多くは母系制をとっていました。家父長制のヨーロッパから来たピューリタンにとってそれは理解のできないことでした。ピューリタンは契約する権限を持たない男性たちと契約を交わし、その契約が守られることがないので、インディアンを嘘つきだと決めつけたのです。
贈与交換は、多くの場合、演説や舞踏を伴うパーティーの形で行われました。ピューリタンにはそれが宴会好きの怠け者と映ったのです。
つまりインディアンたちは、贈与に対して虐殺で返礼するという、自分たちとは対極的な価値観を持つ人々と遭遇することになったのです。
4. インディアンから白人への土地の移転

地図の上はアメリカ合衆国独立(1776年)以前のインディアンと白人との保有地の区分(1775年時点)です。黒く塗られたところがインディアンの居住地です。東海岸を除いて、まだアメリカのほとんどの土地がインディアンの居住地として黒く塗られているのがわかります。
地図の下はそれから120年後の1894年のものです。地図はほとんど真っ白になり、インディアン居住区は小さな染みのような点になっています。120年のあいだに、インディアンは住んでいる豊かな土地から追い出され、砂漠の荒蕪地に追いやられるのです。
その荒蕪地さえも、その後のゴールドラッシュ(新しく金が発見された地へ、金脈を探し当てて一攫千金を狙う採掘者が殺到すること)により、白人から奪われることが多かったのです。
なぜインディアンたちは豊かな土地をやすやすと白人たちに譲り渡したのでしょうか。その主な理由を三つあげることができます。
- 白人からもたらされた疫病による人口の激減
- アルコールへの免疫のなさ
- 恒常的な軍隊をもてない文化であったこと
人口激減については既に触れました。アルコールについては、インディアンには本来飲酒の文化がありませんでした。最初の入植者である白人達はインディアンにラム酒を飲ませて酩酊させ、酩酊状態の中で土地の譲渡契約にサインさせる手法をとったのです。
落雷の凧実験で有名なそして「時は金なり」の格言を述べたベンジャミン・フランクリン(1706-1790)は、「ラム酒+野蛮人=0」という数学の公式を述べたとされます。インディアンにラム酒を飲ませると土地がただで手に入るという公式です。
インディアンには恒常的な軍隊を持つという文化がありませんでした。勇猛果敢なインディアンたちは白人との数多くの戦闘で勝利を収めましたが、彼らの軍隊は戦が終わるとすぐに解散しました。インディアンには平和時の酋長と戦時の酋長がいて、戦時の酋長の権限が継続されることはなかったのです。それに反して、白人の軍隊は解散するということがありませんでした。この文化の違いが圧倒的な勝利を白人にもたらせたのです。
5. WASP(ワスプ)
アメリカ合衆国の社会や文化の特質の核となったのは、WASP(ワスプ)(White Anglo-Saxon Protestant 白人、アングロ・サクソン、プロテスタント)たちでした。アングロ・サクソンというのはイギリス系という意味です。この言葉が生まれたのはずっとのちになってからですが、第1回国勢調査(1790)当時、住民の約80%は白人であり、その白人の約61%はイギリス系でした。建国当時から、 WASP中心の生活様式や価値観が支配的だったのです。このため、独立してからもアメリカの文化はなおイギリスの模倣が多かったのです。
19世紀後半以降のカトリック系やユダヤ系の新移民の増加とともに、 WASPという概念が確立されていくことになります。新移民に対して自分たちの優位性を保つためです。 WASPはカトリック系やユダヤ系を除く白人という意味でしたので、新移民の黄色人種は当然除外され、先住民のインディアン、アフリカから奴隷として連れてこられた黒人も除外されています。
WASPにはプアホワイト(白人低所得層に対する蔑称)は含まれません。人種差別と階級差別がミックスされて、WASPという概念が形成されているのです。
20世紀に至ってなお、政財界の指導者にはWASP出身者が多く、アメリカ社会の支配層を構成するとみなされてきました。
神格化され厳格であった母親たち
WASPは異民族混在の「醜悪な」都心を避けて郊外へ移住、カントリークラブ★がブームになり、1929年までに全米に4500ものクラブができました。
★ カントリークラブ 米国で、都市郊外にあって、テニス・水泳・ゴルフなどの娯楽・保養施設を備えたクラブ。黒人がテニスやゴルフ、スケート、水泳などで頭角を現さなかったのは、これらがクラブ・スポーツだったからだ。タイガー・ウッズでさえ、「この国(アメリカ)には肌の色のため僕がラウンドできないコースがある」(1996年)と発言した。日本では、郊外のゴルフ場の名称に付けることが多い。
上流WASPの家庭は、イギリス・ヴィクトリア朝以上にヴィクトリア朝的でした。
ヴィクトリアニズム (Victorianism) とは、ヴィクトリア朝期の勤勉、禁欲、節制、貞淑などを特徴とする価値観や道徳のこと。19世紀に成長著しかった中流階級の理想を反映し、ピューリタニズムが強く表れている。文学や絵画、彫刻などに強く影響を与えた。行きすぎた厳格さから二重規範(ダブルスタンダード)を生み出すこともあり、しばしば上品ぶった、偽善的といったニュアンスを持つこともある。
WASP の母親は女王として家庭に君臨しました。「メイトリアーカル・マザーmatriarchal mother (厳格な母親)として、子どもたちに「ものに動ぜず、自分をコントロールできていること」を求めたのです。
1863年の奴隷解放宣言までアメリカ南部は奴隷制でしたが、奴隷制の下でWASPの女性は「サザン・ベル(南部の令嬢)」として神格化されました。白人女性が神格化される分、奴隷の黒人女性は白人男性のレイプの対象とされました。レイプの結果生まれた子は同じ奴隷とされ、白人所有者の財産を増やすことになったのです。
サザン・ベルは道徳心の権化に祭り上げられ、それに反比例して、黒人女性は娼婦の役割を受け持つことになりました。黒人男性による白人女性のレイプを恐れ、白人男性は些細な理由で黒人男性をリンチし、虐殺していったのです。
中世ヨーロッパ的なアメリカ
アメリカは中世ヨーロッパ的な社会でもありました。絶対王政の経験のない人々がつくった国だからです。
彼らは中世ヨーロッパの市民や農民と同じく、自警団を持ち、市民が裁判の陪審員となって有罪か無罪を決定します。
アメリカというと新しい土地という印象が強いのですが、ヨーロッパの中世社会から直接にアメリカに文化の伝統がつながっている面があります。ヨーロッパ内部では絶対王政によって大きな変化が生れたのですが、アメリカはその絶対王政を逃れた人びとがつくった国です。
したがってアメリカでは絶対王政の経験がない人たちが国をつくったわけです。たとえばヨーロッパでは一般市民は武装をすることが禁じられておりますし、日本でももちろん禁じられていますが、アメリカではいまでもヨーロッパ中世の伝統を受け継いで、個人が武装することが認められています。ピストルは容易に買えます。許可証がいりますけど、スーパーマーケットでも売っています。(阿部謹也『西洋中世の男と女』)
また中世ヨーロッパと同じく、宗教が生活や精神面に及ぼす影響の強い社会でした。1968年にギャラップ・インターナショナルによって行われた調査の結果によれば、「あなたは天国を信じるか」という問いに、「信じる」と答えたアメリカ人は85%でした。ちなみにイギリス人は54%であり、フランス人は39%でした。
6. インディアンの清掃
イギリスは農業用の土地を獲得するため、先住民を彼らの土地から根こそぎに「清掃(クリアー)」し、そこにヨーロッパ人移民とアフリカ人奴隷を「移植(プラント=植民する)」、いわゆる「清掃と植民」を基本的政策としました。
イギリスからの独立を果たしたアメリカ(1776年に独立宣言)も、イギリスから「清掃と植民」政策を引き継いだのですが、力の弱まった部族には「文明化」という新形態の清掃政策をはじめ、抵抗する部族には軍事力による征服政策を継続しました。
1830年にインディアン強制移住法が成立し、ミシシッピ川の東側に住むインディアンは、同川以西の地への移住を強制されました。大半の部族は、多くの犠牲を払っていわゆる「涙の旅路」Trail of Tearsをたどり西方に移住しました。

1840年には「マニフェスト・デスティニー」Manifest Destiny(アメリカ大陸への膨張は天命である、との意)の名の下で、テキサス、大平原、オレゴン、カリフォルニアの先住諸部族が新たに「清掃」の対象に加えられました(絵は1872年に描かれた「アメリカの進歩」)。
合衆国軍による軍事的征服に対する大平原先住諸部族の武力抵抗は、1870年代にクライマックスを迎えました。しかし軍事力の格差は大きく、1886年に武力抵抗は終わりを告げ、1890年には、スー族に対する女性子どもを含めた無差別虐殺が行われ、インディアンたちは決定的に敗れ去ったのです。
「涙の旅路」
アメリカ政府は先住民族の各部族を属国と規定、インディアン駆逐政策を公式に掲げ、協定の無理強いや武力による実力行使で多くの部族を不毛な地に強制移住させました。
1万7000人が銃を突きつけられ、着のみ着のまま干ばつの地を何百キロも歩かされ、4000人が途中でのたれ死にしたというチェロキー族の「涙の行程」、米軍基地から広まり、10万人のアメリカ・インディアンを死にいたらせたとされる天然痘の流行など、今なら国際世論が黙っていない事実上の民族大量虐殺も平然と行われていたのです。(『太ったインディアンの警告』)

【図像説明】1830年に「インディアン移住法」が施行され、チェロキー族、チカソー族、チョクトー族、クリーク族 、セミノール族の、5つのインディアン部族が故郷のミシシッピ川の東から根こそぎ追い出され、数十年かけて大陸をほぼ横断させられ、現在のオクラホマ州の東部にあるインディアン準州と呼ばれた場所に徒歩で移住させられた。なかでも最も悪名高い強制移住は、チェロキーの「涙の旅路」(1838年)である。
フロンティア
インディアンが「清掃」された土地に、ヨーロッパからの白人移民が次々と流れ込みました。南部には黒人奴隷がおり、WASPは貴族主義的な生活を送ることができました。中西部のフロンティア(新天地)は、「努力するものが報われる」世界でした。ヨーロッパでの貧困層も、ミドルクラスになることが可能でした。「アメリカンドリーム」の実現です。
フロンティアでは、健康で、勤勉で、頭の回転が速ければ、たいていの場合に成功しました。広い農場を手に入れるという夢を実現すれば、それが自信を生み、楽天的な性格を育て上げます。荒々しくて、それでいて親切で、助け合うようなフロンティア・スピリットが、アメリカ人の性格として19世紀に身についたのです。
開拓者は、人間はすべて善良だと信じました。フロンティアのたいていの州では、選挙権はすべての白人に平等に与えられました。女性の参政権も1920年の憲法修正で全国的に認められたが、フロンティアではたいていの州がそれよりも先に、男女平等に参政権を認めていました。デモクラシーはフロンティアで育ったのです。
レディファースト
フロンティアでは女性もたくましく働かなければなりませんでした。それにもかかわらずヴィクトリア朝レディというジェンダー観はフロンティアにまで持ち込まれていました。つまり労働をする女性ではなく、家庭の天使である女性像です。
弱い女性を崇拝し庇護するという、騎士道に端を発する「レディファースト」も、ヨーロッパ以上にアメリカで重視されるマナーでした。
イギリスであれ、アメリカであれ、ヴィクトリア朝の女性たちがスズメバチのようなシルエット――張り出した胸と腰、ほっそりした21インチ(約53センチ)くらいのウエストというスタイルを理想とし、こぞってコルセットで腰を締めつけていたことはよく知られている。(…)
1867年アメリカの開拓地生まれのローラ・インガルス・ワイルダーは、少女時代の思い出をもとに書いたシリーズの中の一冊、『大草原の小さな家』(1941)でコルセットをつけ始めたヒロインの悩みを描いている。ローラは14歳。女の子が髪を上げ、長いスカートをはくようになったら、どうしてもコルセットをつけなければならない。彼女は息を深く吸うこともできない鋼鉄のコルセットが苦手だ。従順な長女メアリーは寝ている時もつけているし、母は新婚当時、自分のウエストが夫の片手でつかめたことを自慢し、ローラにも身体を矯正するよう忠告するのだが、ローラはこれが苦痛でならない。(岩田託子、川端有子『図説 英国レディの世界』)
寄宿学校によるインディアン同化政策
一方で大量虐殺から生き残ったインディアンは、不毛な地に囲い込まれ、伝統の食源である狩猟・採集や農耕の道を断たれ、アメリカ政府が配給する食糧で飢えをしのぐようになります。
子どもたちは白人社会への同化政策の一環として、インディアン寄宿学校に強制的に収容されます。寄宿学校のスローガンは、「インディアンを殺し、人間として救う」というものでした。
1878年に始まった寄宿学校制度は、アメリカ政府の公式インディアン政策となって全米に広がり、1928年までに全米で500校が開校し、総計10万人の子ども達が送り込まれました。
白人たちの寄宿学校はエリートを育成するためのものでしたが、インディアン寄宿学校は、アメリカ・インディアンの伝統文化を完全に奪い、白人同様の価値観を持ち白人社会に貢献するアメリカ人に変身させることを目的とするものでした。
母族語の使用や伝統の儀式やふるまいは愚鈍で野蛮な行為として堅く禁じられ、それを破れば厳しい体罰で罰せられました。

【図像説明】「カーライル・インディアン工業学校」のインディアン生徒たち、1900年頃。この施設は白人キリスト教徒によって経営され、「保留地」のインディアンの少年少女達を親元から強制的に取り上げ、先祖伝来の宗教、言語を禁止して、「インディアンを殺し、人間を救う」を合言葉に、キリスト教や欧米文化の学習、英語教育などを行っていた。

カナダの「カペル・インディアン寄宿学校」。インディアン生徒の親たちは施設の立ち入りを禁じられ、子供に面会するためには学校の外で野営しなければならなかった(1885年)
努力したものが報われない社会
1928年に義務教育としてのインディアン寄宿学校制度は廃止されましたが、実際には、多くの部族にとっては、インディアン寄宿学校は居住地の近くに移っただけでした。
そこでは以前と同様に部族の言語で話すことも禁止され、軍隊式の体罰や性的、精神的虐待も横行。傷ついて帰れば、すさみきった居住地の現実と世代の断絶が待っていました。
部族政府によるインディアン居住地の自治と州内での治外法権が認められ、宗教、儀式の自由がインディアン社会に戻ったのは、黒人の市民権運動に刺激され、アメリカ・インディアンの権利運動が活発化し、一般アメリカ人の世論も動いた1970年代末になってからのことだったのです。
感受性が強い子ども時代にたたき込まれた劣等感からアメリカ・インディアンとしての民族の誇りを失い、インディアンであることを忘れて白人の社会で生きていこうとした人たちの多くは、万民平等をうたうアメリカ社会が実は偏見と差別に満ちていて、自分たちが成功できるチャンスが少ないことに挫折しました。インディアンにとってアメリカは、「努力したものが報われない社会」だったのです。
こうして、ふたつの世界の狭間で自分の存在価値が見いだせなくなった、喪失の世代が増えていきました。
7. 米軍兵士になって覚えた白人食の味
アメリカ・インディアンの食生活の欧米化を促進することになった大きな要因は、男性の多くが米軍兵として軍隊生活を体験し、そこで慣れた白人食の習慣を居住地に持ち込んだことだといわれています。
一般社会では努力しても報われることのなかったインディアンの若者も、軍隊に入ると別でした。第二次世界大戦(1939-45)では、4万4000人以上の男性が米軍兵となり、めざましい活躍をしたとされます。当時のアメリカ・インディアンの総人口が35万人にすぎなかったことを考えれば、極めて大きな人口比でした。ベトナム戦争(1955-75)に出兵したアメリカ・インディアンの男女も4万2000人を超え、そのうち90%は志願兵でした。
アメリカ・インディアンの米軍への志願率が今でも高い背景には、貧しく荒廃したアメリカ・インディアン社会の現状に目をつけ、「将来役立つ技術が身につき、退役した後に大学に進学し奨学金がもらえる」といった特典を盛んに宣伝して、米軍がアメリカ・インディアンの居住地でのリクルートに力を入れてきたという事情もあります。アメリカン・ドリームへの入り口が軍隊だったのです。(『太ったインディアンの警告』より)
第二次大戦後に始まった、肥満、生活習慣病との闘い
第二次大戦前まではアメリカ・インディアンの社会では皆無に近かった肥満や糖尿病は、50年代、60年代を通じて伝染病のように増え続け、70年代後半には、その蔓延が疑いようのない事実となっていました。
民族別にみた糖尿病発症率では、アメリカ・インディアンは米国の中だけではなく世界の民族中のトップとなっています。
つまり白人社会への同化が進み、自給自足の生活、季節の自然の恵みを生かした伝統食から離れ、現代アメリカの食生活とライフスタイルを踏襲したことが、アメリカ・インディアン社会の悲運の始まりとなったのである。
周囲に腎不全で亡くなる人や失明する人、足や腕の切断を余儀なくされる人々が増えて、初めてアメリカ・インディアンの社会は以前には体験したことがなかった「白人の病気」の恐ろしさを知りました。
同時にアメリカ・インディアンの社会に起こった異変は、肥満や糖尿病の恐ろしさを目に見える形で世界に警告することにもなったのです。(『太ったインディアンの警告』)
8. 米軍基地化と本土返還で悪化した沖縄の人々の食生活と健康
同じ現象は第二次大戦後の沖縄でもみられました。
第二次大戦と敗戦で食糧危機に陥った沖縄の人々が、戦後に米、小麦粉、砂糖、油といった食物配給に頼らざるを得なくなった状況は、アメリカ・インディアンの歴史にも似ています。
沖縄は少しずつ経済復興し、1961年には輸入肉の管制貿易から自由貿易に移行。1950年代、60年代に消費者の購買力増大に呼応して加工肉の缶詰などの輸入も増大、肉など高カロリー、高脂肪の欧米食の摂取量が増えていった過程もアメリカ・インディアンの戦後の歴史に似ています。
そうした食生活の変化に呼応するように、第二次大戦直後には日本本土の子ども達より痩せていた沖縄の子ども達の体重は、70年代には急速に差を縮め、70年代後半には本土平均を上回りました。(…)
こうした栄養摂取の変化が、沖縄の平均寿命を低下させ、肥満率や生活習慣病の発症率を上昇させていったのは、研究者にとっては疑いようがないのです。(『太ったインディアンの警告』)
太ったインディアンの警告は、他人事ではない
アメリカ・インディアンの肥満、生活習慣病増加の背景には、アルコール依存症の蔓延という社会問題もひそんでいます。
肥満率の高さで知られるアリゾナのピマ族の場合など、成人の10人に一人はアルコール依存症の治療カウンセリングを受けています。
連邦インディアン衛生管理局の統計によれば、アメリカ・インディアンがアルコール性肝硬変で死亡する率は全米平均の18倍。アメリカ・インディアンの死因のトップ10のうちの4因は飲酒による事故、慢性肝炎や肝硬変、自殺、他殺となっています。
彼らの間でアルコール依存症が増えたのは、伝統文化が弾圧され、アメリカの白人社会への同化を強いられ、個人として、また部族社会としての自信とプライドを失ったのが大きな要因だったと考えられています。(『太ったインディアンの警告』より)
巨大な米軍基地を抱え、5万人近くの在沖米軍人・軍属・家族★と同居する沖縄において、アメリカ・インディアンからの警告は他人事ではありません。アメリカ・インディアンの歴史を含めたアメリカ人と、その家族観を知る必要があるといえるでしょう。
★ 沖縄県基地対策課によると、2011年6月末時点で、在沖米軍人・軍属・家族の人数は4万7300人となっている。
【参考文献】
エンカルタ2000
岩田託子、川端有子『図説 英国レディの世界』(2011年、河出書房新社)
マックス・ウェーバー(大塚久雄訳)『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』(1989年、岩波文庫)
エリコ・ロウ『太ったインディアンの警告』(2006年、NHK出版 生活人新書)
とうもろこしおばあさん ミダス王 ロード・オブ・ザ・リング
1. はじめに
前回の講義では、近代家族にとって自助グループが伝統社会的なコミュニティの代わりを果たすのではないのかという視点から、近代家族とコミュニティの再構築の問題を考えてきました。近代家族がコミュニティからの引き篭もりによって誕生したのだとするならば、コミュニティとのかかわりの再構築が近代家族にとって大きな課題となります。その再構築の手がかりとして見えてきたのが、アディクションにともなう自助グループの存在でした。
自助グループでは「言いっ放し、聞きっ放し」というコミュニケーションの方法がとられています。それは交換価値的なコミュニケーションではなく、互いの存在をそのまま受け入れる存在価値的コミュニケーションだといえます。そのようなコミュニケーションが現代の社会においてどのような意義を有するのか、それを近代家族と資本主義社会とスピリチュアル(霊的なもの)をテーマにして考えてみたいと思います。
2. 家族・産業・宗教
アディクションは近代家族の構造自体がもたらす病といえます。その構造からの脱却には、近代社会に張り巡らされている知の枠組みを超えることが必要とされたのだということができます。
理性や意志などといった近代を形成した知の枠組みは、アディクションの前では無力でした。無力であるということを認める〈底つき状態〉から、アディクションは回復への契機をもつことになります。その実践的な回復プログラムのなかで有効であったのは、久しく忘れられていたハイヤー・パワーや霊的な目覚めなどといった宗教的なキーワードでした。
歴史的に最初に成功したセルフヘルプグループであるアルコホーリクス・アノニマス(Alco
holics Anonymous匿名のアルコール依存者たち 以下AA)は、飲酒をしないで生きるというシンプルな目的を達成するために、実践的なプログラムを編み出しました。
AAのプログラムで特徴的なことは、個人であることにまつわる近代的な意義づけを解体し、スピリチュアルなものを再評価するという点にあります。AAの回復プログラムである「12のステップ」では、冒頭に「われわれはアルコールに対し無力であり、生きていくことがどうにもならなくなったことを認めた。」という確認から入ります。アディクションに対して無力であることを認めるという自己認識から、回復プログラムは始まるのです。そして「われわれは自分より偉大な力が、われわれを正気に戻してくれると信じるようになった。」というハイヤー・パワー(偉大な力)の肯定があります。
このハイヤー・パワーというのがなかなか理解しにくいイメージなのですが、これをキリスト教の神ととらえずスピリチュアルなものととらえるならば、普遍的なものであるといえます。世界各地の様々な社会の様々なシャーマン(超自然的存在と直接接触・交流・交信する役割を担う人)やメディスンマン(病気を治す超能力を持っていると信じられている人)は、現代社会においても絶えることなく存在し、多くの人々がその治癒行為を受けています。それは土俗的な宗教であるにとどまらず、高度な資本主義社会に住む人々にさえも、その存在が求められているのです。
スピリチュアルなものは近代的な理性や合理主義からは、迷信に近いものとみなされますが、そのような見方が確立するのは西欧においても200年ほど前のことであり、多くの社会においてはつい最近まで、迷信ではなく宗教として信じられていたのです。近代的な知性の枠組みでは、まだ公的に認められることは少ないのですが、実際にはスピリチュアルなものに救いを求める人たちは多いのです。近代的な思考の枠組みがそれを公的なものとして認めないだけです。
また児童文学のファンタジーの世界やアニメの世界にはスピリチュアルなものが満ちあふれています。それはフィクションとして公認されているのですが、なぜそのようなスピリチュアルなものが求められ続けていられるのかについて、近代的な知性の枠組みで真剣に考えられることはありません。それは子どもの世界の物語であり、大人の世界では公認されないものとしてかろうじてその存在が認められているといってもよいでしょう。しかし大人の世界で公認されないだけで、スピリチュアルなものに対する需要が絶えることはありません。
ハイヤー・パワーはそのようなスピリチュアルなものと理解してよいでしょう。近代的な知性の枠組みでは、スピリチュアルなものの存在を的確にとらえることはありませんでしたが、過去から存在し、現在においても必要とされるものを、アディクションの底つきの状態で出会ったのだとみるならば、AAはアディクションをとおして近代的知性の枠組みの限界を超えたのだとみることができます。
伝統的な社会においてコミュニティと家族、個人が不可分なものであったように、スピリチュアルなものの存在も、コミュニティと家族、個人を結びつけるものとして重要な役割を果たしていました。しかし近代家族において家族とコミュニティとのかかわりが二次的なものとなり、家族と個人が爆発的情愛で結び付けられたように、近代社会においてスピリチュアルなものは二次的なものとされ、理性と合理主義が知の枠組みとなります。
しかしアディクションが個人の意志力によって克服することができず、家族の協力によっても回復することのできない病気であるとするなら、二次的なものとされたコミュニティやスピリチュアリティも再構築され、再評価されなければならないでしょう。アディクションからの回復において、自助グループという新たなコミュニティを再構築することが有効でしたが、同じように自助グループの中で、スピリチュアルなものの再評価も必要とされるのです。
個人と家族、コミュニティが不可分の三位一体の存在であるように、人間の社会は、家族形態と産業構造と宗教形態が三位一体のメカニズムとして機能しています。近代家族が家族のコミュニティからの引き篭もりによって誕生したように、近代産業社会もスピリチュアルなものを排除することによって成立したのだとみることができます。
3. 産業構造と宗教形態との逆説的な関連
産業構造を、モノを介してのコミュニケーションとみるならば、産業構造は常にスピリチュアルなものの逆説的な表現として成立してきたものとみることができます。なぜならばモノには本来、自然界の精霊や異界=他界の霊魂、人間界における最初の所有者の霊魂が込められていたからです。その霊的なモノと逆説的な関係を築くことにより、産業構造は成立することができたものとみることができます。つまり霊的な世界とのコミュニケーションがモノを介して成立したとき、はじめて産業構造は、人間的なものとして成立するのです。
狩猟採集社会のアメリカ・インディアンにとって、農耕は大地を傷つける行為だとされました。自然の恵みによって生きていた狩猟採集民は、恵みをもたらす自然への感謝を表わすことが宗教形態でした。その自然の秩序に人間が手を加えることなどは冒涜的な行為だったのです。
白人よ、お前たちは私に、大地を耕せ、と要求する。この私に、ナイフを手にして、自分の母親の胸を裂け、と言うのか。そんなことをすれば、私が死ぬとき、母親はその胸に、私を優しく抱きとってはくれないだろう。(中沢新一訳『インディアンの言葉』)
白人たちが大地を耕せと要求したのは、インディアンから土地を取り上げるためでした。狩猟採集社会が広大な土地を必要とするのに対して、農耕生活はより狭い土地でも生存することが可能だったからです。しかし狩猟採集民にとって農耕は、母親の胸を切り裂くのに等しい行為だったのです。
一方、狩猟採集社会から農耕牧畜社会への移行への過程にあったアメリカ・インディアンに、「とうもろこしおばあさん」という民話があります。こんな話です。
むかし、アメリカに住むインディアンは、男たちは、野牛をとり、女たちは、いもを掘って暮らしていました。あるとき、小さな村に、ひとりのおばあさんがやってきて、「ここに ひとばん とめてくださらんか」とたのみました。インディアンの若者は、こころよくおばあさんを泊めてあげました。つぎの日、大人たちが、狩りやいも掘りに出かけてしまうと、おばあさんはテントの中で、なにやらおいしそうなものを作りました。それは、今まで見たこともないパンでした。みんなで食べてみると、とてもおいしいのです。「やぎゅうでも、いもでもない。なんだろう、このおいしいものは」と聞くと、「それは、とうもろこしというもんだよ」とおばあさんは、答えてくれました。でも、どこで手に入れたかは、どうしても教えてくれませんでした。ふしぎに思った若者は、ある日、狩りに出かけたふりをして、戻ってくると、こっそりテントの中をのぞいてみました。すると、中ではおばあさんが着物の裾をめくり自分の腿を掻いていました。すると腿からはとうもろこしの粒がぽろぽろと落ち、やがて床に溢れました。若者に見られたことに気づいたおばあさんは、次の朝、若者を平原に連れて行き、「枯れ草に火を点けなさい」といいました。そして「私の髪をつかんで灰の上を引きずりまわしなさい。最後には私を燃やしておしまい。怖がらなくてもいい。跡には小さな草の芽が出てくるだろう。そして三度丸い月が空に昇ったら見に来ておくれ」。わかものは、おばあさんにいわれたとおりにしました。
とうもろこしは、こうしてインディアンに伝わりました。それからというもの、インディアンはとうもろこしをみると、おばあさんを思い出し、一粒も無駄にしないで大切にしています。(秋野和子再話、秋野亥左牟画『とうもろこしおばあさん』より)
この話には、狩猟採集社会から農耕牧畜社会へ移行するときのドラマが描かれています。農耕牧畜は初期の段階では焼畑から始まりますが、その平原を焼くときの恐れとおののき、そして穀物を与えてくれることへの感謝が物語られています。穀物を栽培するということは、母なる大地を焼き、「殺害」する行為でもありました。そのことによって母なる大地から穀物が人間へもたらされます。
そこには神を殺害せざるを得ないという逆説があります。狩猟採集社会においては、自然に手を加えることはタブーとされているのですが、農耕牧畜社会においては、自然に手を加え、神を殺害するという逆説によってのみ、自然からの恵みがもたらされます。この逆説を成立させることができたとき、農耕牧畜社会は狩猟採集社会から続くスピリチュアルなものを再構築することができたのだということができます。
4. スピリチュアルなものの排除
近代資本主義社会は、このようなスピリチュアルなものを排除して成立してきました。社会学者のマックス・ウェーバー(1864-1920)は、厳格で禁欲主義的なカルヴィニズム[1]のなかで、スピリチュアルなものが排除されていったのだとみています。カルヴィニズムの特徴は、誰が天国に行き、誰が地獄に落ちるのかは、前もって神に定められているとみたことです。ウェーバーはそこから信者の内面的孤独化の感情が生まれたのだとしています。
われわれが知りうるのは、人間の一部が救われ、残余のものは永遠に滅亡の状態に止まるということだけだ。人間の功績あるいは罪過がこの運命の決定にあずかると考えるのは、永遠の昔から定まっている神の絶対に自由な決意を人間の干渉によって動かしうると見なすことで、あり得べからざる思想なのだ。(中略)この悲愴な非人間性をおびる教説が、その壮大な帰結を身にゆだねた世代の心に与えずにはおかなかった結果は、何よりもまず、個々人のかつてみない内面的孤独化の感情だった。(マックス ウェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』)
つまり人間が良いことをしようが悪いことをしようが、天国に行く者は前もって決まっているということです。カルヴィニズムではすべての人が救われるわけではありません。一部の人だけなのです。しかも誰がそうなのかは、神様しか知らないわけです。
その中で人々は孤立感に陥ります。誰が救われるのかわからないので、疑心暗鬼しかないからです。疑心暗鬼の中ではコミュニティへの信頼感は生まれません。ただ不安感の中で神とつながるしかないのです。カルヴィニズムは個人を徹底した不安の感情に突き落とし、その不安の感情から神と直接つながることを求めたのだといえます。
その強烈な不安感は、教会という場やスピリチュアルな儀式に救いを求めることはできません。教会に通おうがスピリチュアルな儀式に参加しようが、そこには救われるという保証はないからです。ウェーバーはそこに呪術からの解放をみたのです。
すなわち〔カルヴィニズムが〕教会や聖礼典による救済を完全に廃棄したということこそが、カトリシズムと比較して、無条件に異なる決定的な点だ。世界を呪術から解放するという宗教史上のあの偉大な過程、すなわち、古代ユダヤの預言者とともにはじまり、ギリシャの科学的思考と結合しつつ、救いのためのあらゆる呪術的方法を迷信とし邪悪として排斥したあの呪術からの解放の過程は、ここに完結をみたのだった。(ウェーバー前掲書)
呪術からの解放とは、合理化する思考法のことです。このような呪術からの解放は、スピリチュアルな感覚や感情を迷信として葬り去ります。そのような内面的孤独化と合理的な思考法により、資本主義の精神は誕生したのだとウェーバーはみています。つまり宗教構造の中からスピリチュアルなものを排除することにより、近代資本主義は誕生したのだということです。
5. 無限に自己増殖する資本主義の富
ウェーバーがいうように、魂の救いに関する強烈な不安感から近代資本主義が誕生したのだとみるならば、資本主義の富は無限に自己増殖を続け、とどまることはありません。狩猟採集社会における獲物や収穫物は自然からの贈与であり、農耕牧畜社会における穀物の豊饒も大地からの贈与としてスピリチュアルなものとされていました。しかし資本主義の富は不安から生み出され、スピリチュアルな要素は排除されています。スピリチュアルなものを排除しているからこそ、資本主義の富は無限に自己増殖を続けることが可能となっているのだといえます。
近代資本主義社会は、富の無限な自己増殖活動によって引き起こされました。富が無限に自己増殖を続けるということは、経済の右肩上がりを前提とする社会ができあがったということを意味します。その経済の右肩上がりを前提として近代家族は組織化されています。
近代家族は近代資本主義社会に適合的な家族形態であったのですが、そのためにスピリチュアルなものが家族から排除されることになりました。AAでいうところのハイヤー・パワーとは、スピリチュアルなものと再び出会うことにより、魂の救いに関する強烈な不安感から回復することを意味します。
近代資本主義社会は、富の無制限な蓄積によって引き起こされました。富の無制限な蓄積は近代固有の産業形態であるということができます。近代以前の社会においては、富の無制限な蓄積は公認されることはありませんでした。富は人を魅惑するものであるとともに、その蓄積は不吉なものとされていました。
ギリシャ神話には、触れるものすべてを黄金に変えてしまうというミダス王の神話があります。ミダス王はディオニュソスという豊穣とブドウ酒と酩酊の神からその不思議な力を授かります。しかし食べ物が硬くなり、飲み物が黄金の氷に固まるのを見たそのとき、ミダス王はこの贈り物が破滅のもとであることを悟ります。そしてディオニュソスにその不吉な能力を取り去ることを願ったのです。
ミダス王の、触れたものすべてを黄金に変えてしまうという不思議な力は、無制限に富の拡大再生産を続ける資本主義の構造と同じです。ミダス王はその能力を不吉なものとし、取り去ることを願うのですが、近代資本主義は無限の自己増殖運動を自己目的化します。
J.R.R.トールキン作の『ホビットの冒険』(映画:ロード・オブ・ザ・リング)では、妖精界や人間界など世界のすべてを支配する力を持つ指輪が登場します。その指輪をひょんなことから手に入れてしまったのは、妖精界の中でももっとも平和主義者で欲の少ないホビット族の少年フロムです。
この指輪を巡って妖精界や人間界を巻き込んだ戦いが繰り広げられます。この指輪に魅入られた者は、指輪から離れることができなくなり、指輪に人格まで支配されてしまいます。この指輪を消滅させるためには、「滅びの亀裂」という火山の火口に指輪を投げ入れるしかありません。欲の無いフロムでさえ何度も指輪に魅入られそうになるのですが、友人であり忠実な従者であるサムの助けで指輪の誘惑から逃れます。そしてサムとともに指輪を「滅びの亀裂」に投げ入れるのに成功するのです。
『ロード・オブ・ザ・リング』の指輪は、資本主義の自己増殖する霊力の象徴であるともいえるでしょう。それを手にする者はそれに魅入られてしまい、人格さえも支配されてしまうのですから。またアディクションの状態ともよく似ています。指輪をアルコールや薬物などと置き換えてみると、構造は同じです。その指輪を手に入れると、もはや指輪から逃れることができなくなるからです。
その指輪を消滅させることができるのは、争いを好まず欲の無いホビットのフロムだけであり、フロムが指輪に魅入られて他人を信じなくなったときでさえ、フロムをサポートし続けたサムの友情だったのです。
6. 生産型社会から消費型社会への転換
フランスの社会学者マルセル・モース(1872-1950)は、主著『贈与論』(1924年)において、売買交換に先立つ交換形態として贈与交換があることを提唱しました。贈与交換とは贈り物をし、贈り物にはかならず返礼があることを前提とする交換形態です。
モースが贈与交換を提唱する前までは、売買交換の以前の交換形態は、物々交換であるとみなされていました。物々交換は、貨幣などの媒介物を経ず、物品と物品を直接に交換することをいいます。
物々交換という概念は、社会進化論的な概念でした。市場的売買交換を交換のあるべき姿だととらえ、物々交換をまだその段階に達していない未開の状態だとみたのです。つまり社会進化論的にいえば、貨幣などの媒介物が欠けている物品の交換は、未開のものであり、いずれ市場的売買交換へ進化しなければならないものとされていたのです。
モースはこのような社会進化論的な見方に異議を唱えました。贈与交換こそが人類史に普遍的にみられた交換形態であり、市場的売買交換が普及した現代においてさえ、贈与交換は行なわれ続けているとしたのです。
モースの贈与論は、1970年代に再評価を受けることになります。1970年代は、資本主義の先端地域において、経済の中心が生産型社会から消費型社会へと変換した時代でした。生産型社会においては、市場的売買交換を拡大再生産することが至上の課題であり続けたのです。しかし国内市場は、消費者の購買意欲があるあいだは、「作れば売れる」時代であったのですが、生活必需品がひととおり行き渡ってしまうと、「作れば売れる」時代は終わってしまいます。
消費者の購買意欲は、商品を買うこと自体より、商品の差異化を買うほうに向かいます。商品自体よりも商品の持つ他の商品とは異なる差異が価値となるのです。経済の中心がそのような段階に達すると、生産の流れは大きく変わり、「売れるものが作られる」時代へと変化します。
この変化は大きな変化でした。「売れるものが作られる」ということは、「売れるもの」しか「作られない」ということを意味するのです。生産型社会においては、生産する主体が経済活動の動向を支配していました。しかし消費型社会においては、消費者の動向が経済活動を左右するのです。それは経済活動の主役が、企業から消費者へ移ったことを意味します。消費者が購買意欲をもたないかぎり、経済は活性化しないのです。
それまでは企業が成長していくことがそのまま労働者の所得向上につながりました。ですから社会的価値観をつくりあげるのは企業でしたし、国の政策も企業のバックアップにつとめていれば、国の経営がうまくいっていたのです。国民経済というパイが増えることが、そのまま国民生活の向上につながったのです。
しかし消費型社会へ移行すると、パイが増えることに期待することはできなくなります。購買意欲というパイ自体はすでに充たされているからです。そうするとパイの拡大ではなく、パイの切り分け方が重要な政策課題となります。パイをいかに分配するかで経済活動が安定してくるかどうかが問われるようになってくるからです。
ここで二つのことが課題となります。一つは、パイの拡大からパイの切り分けにシフトが変更されたかどうかの問題です。もう一つは、パイの切り分けがどのようになされるかです。どちらの課題もスムーズに移行されなければ、経済活動は停滞するか低下することになります。
消費型社会へ移行するとともに、パイの拡大ではなく、パイの分配に経済活動の主軸が移ります。その時代にモースの『贈与論』が再評価されたのです。市場的売買交換よりも贈与交換が人類史において普遍的であるという指摘です。この視点は、パイの分配に経済活動の主軸が移るという時代において、パイの分配に理論的根拠を与えるものでした――残念ながら日本は、パイの分配に主軸を移すというシフトチェンジに遅れをとってしまいました。
消費者が購買意欲を維持するような政策はとられなかったのです。それどころか新自由主義という新たな拡大再生産へ舵をきったのです。その結果、経済活動は停滞を続けることになってしまいました。
1970年代という時代は、欧米や日本など資本主義の最先端を行く地域において、資本主義社会の構造が、生産型社会から消費型社会へと移行する画期的な時代でした。その時代にモースの『贈与論』が見直され、トールキンの『指輪物語』が熱心に読まれたのです。それは来るべき時代の課題が、富の増殖ではなく富の分配にあったことを、そして富の増殖がアディクションを招くことを予兆していたものではないかと思われます。
参考文献
J.R.R.トールキン『ホビットの冒険 下』(2000年、岩波少年文庫)
ブルフィンチ『ギリシャ・ローマ神話』(1978年、岩波文庫)
マックス ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』(1989年、岩波文庫)
マルセル・モース『贈与論』(2009年、ちくま学芸文庫)
ミシェル・ピルクマン編、中沢新一訳『インディアンの言葉』(1996年、紀伊國屋書店)
秋野和子再話、秋野亥左牟画『とうもろこしおばあさん』(1982年、福音館)
『ロード・オブ・ザ・リング(DVD)』(2014年、ワーナー・ホーム・ビデオ)
[1] カルヴィニズム(Calvinism)とは、すべての上にある神の主権を強調する神学体系、およびクリスチャン生活の実践である。宗教改革の思想家ジャン・カルヴァンにちなんで名づけられている。ウェーバーはカルヴィニズムの中に「個々人のかつてみない内面的孤独化の感情」を見、それが資本主義の精神を生み出したとした。
贈与交換と家族
贈与交換と家族
1. 狩猟採集社会における家族
人類の初期の産業構造(=経済活動)は狩猟採集社会でした。そこでは獲物の動物や果物や根菜などは自然から人間に贈与されました。この贈与関係を維持するために、人間は自らをスピリチュアルなものとし、自然もまたスピリチュアルなものと見ました。そしてスピリチュアルなものとして人間と自然が交歓したのです。
それはどういうことかというと、動物や植物、昆虫、太陽や月、星、人間などの大宇宙に存在するものを、その外形や存在形態の違いにかかわらず、すべて人間どうしのように会話を交わすことができ、交際できるものとみなしていたということです。
たとえばアマゾン川源流近くに住むトゥクナ族の狩人モンマネキの神話では、主人公がカエルや鳥やミミズやインコと次々と結婚しては別れるという話が続きます。別れる理由は、主人公が配偶者に満足しているのに、主人公の母親が嫁に意地悪をして追い出すというだけですから、人間世界の姑による嫁いじめの話とさほど変わる構図ではありません(クロード・レヴィ・ストロース『神話論理Ⅲ 食卓作法の起源』より)。
狩と獲物の関係で言うと、北海道のアイヌをはじめとする狩猟採集民の世界では、獲物を狩るのではなく、その動物の身体の中に閉じ込められていたスピリチュアルなものを解放してあげるのだという考えがあります。そのスピリチュアルなものを歓待することによって、動物はその身体を土産として人間たちに与え、仲間の元に喜んで帰っていくという考えです。そして仲間の元で人間たちから受けた歓待の話をして、今度は仲間を引き連れて人間たちの歓待を受けにやって来るというものです。
ただし人間が人間という存在のままで動物たちを歓待することはできません。人間もまた自分の身体を離れ、スピリチュアルな存在となって動物たちを歓待するのです。人間自身がスピリチュアルな存在となって動物や植物など自然の様々なスピリチュアリティを歓待することによって、スピリチュアリティとしての自然は、歓待に対する返礼として、自分の身体を人間に贈与するのです。この贈与交換によって人間世界に富がもたらされます。自然は人間に贈与を与えるものですので、狩猟採集社会において、自然を傷つける行為はタブーとされたのです。
狩猟採集社会において家族は、定住する必要はありませんので、家族構成員も固定される必要はありませんでした。ですからヘアー・インディアンのように生物学的な母親が子どもを育てるのではなく、「子どもは育てられる人が楽しんで育てる」ものでした。またアンダマン諸島人のように、たがいの家の子どもを交換することが、礼儀であり、友愛の印だったのです。
2. 農耕牧畜社会における家族
農耕牧畜社会においては、野生の動物を飼育し、穀物を栽培しなければなりません。そこでは自然は人間に敵対するものとなります。野生の動物を飼育し、穀物を栽培することは、自然界の秩序とは異なる人間界の秩序をつくり出すということでした。
つまり人間の世界というミクロコスモス(小宇宙)と自然界というマクロコスモス(大宇宙)が分離するのです。しかし飼育された動物も栽培される穀物も、もともとはマクロコスモスに所属するスピリチュアルなものでした。ここで宗教形態は逆説的なものになります。
動物を家畜化し、穀物種を栽培種化することによって、自然のスピリチュアリティではなくて、スピリチュアリティを超えた神という概念をつくりだし、その神を殺害する、あるいはその神のために動物や人間を犠牲に捧げるというドラマティックな宗教形態になります。大宇宙の一部を神として崇め、その神のために犠牲を捧げなければならないという、崇拝と血腥さが一体となった逆説的な宗教形態がつくりだされるのです。
狩猟採集社会において自然は人間に敵対するものではなく、贈与を与える存在でした。農耕牧畜を始めることにより、自然は人間に敵対する存在となります。雨や風など季節の巡りが順調になされないならば、旱魃や洪水などが引き起こされてしまいます。そこで自然を人間の希望にかなうように願うことが宗教となり、自然を家畜化し、栽培化することで労働が発生します。
今帰仁村の古宇利島の神話に、労働発生の神話があります。
むかしむかし古宇利(ふい)島(運天港の入口にある小さい島)に男の子と女の子が現れた。二人は裸体でいたが、まだ愧(は)ずるという気は起こらなかった。そして毎日天から落ちてくる餅を食って、無邪気に暮らしていたが、餅の食い残しを貯えるという分別が出るや否や、餅の供給が止まったのである。そこで二人の驚きは一通りでなく、天を仰いで、(伊波普猷『古琉球』)
たうたうまへされ、たうたうまへ(お月様、もしお月様)
大餅(おほもち)やと餅お賜(た)べめしようれ(大きい餅を、太い餅を下さいまし)
うまぐる拾うて、おしやげやべら(赤螺(あかにし)を拾うて上げましょう)
と歌ったが、その甲斐もなかった。彼らはこれから労働の苦を嘗(な)めなければならなかった。そして朝な夕な磯打際にウマグルなどをあさって、玉の緒を繋いでいたが、ある時海馬の交尾するのを見て、男女交媾の道を知った。二人は漸(ようや)く裸体の愧ずべきを悟り、クバの葉で陰部を隠すようになった。今日の沖縄三十六島の住民はこの二人の子孫であるとのことだ。
天から餅が落ちてくるというのは、狩猟採集社会における自然からの贈与にあたります。その餅を貯えるという知恵が発生したときに、天から餅は降らなくなり、労働の苦しみが発生するのです。そのことは狩猟採集社会から農耕牧畜社会への移行を暗示しています。
つまり自然からの贈与は絶え、人間は家畜の世話や畑を耕すといった労働によらなければ生活できない存在となったのです。そこには「とうもろこしおばあさん」とは異なった、狩猟採集社会から農耕牧畜社会への移行のドラマが語られています。古宇利島の神話では食べ物を「貯える」という農耕牧畜社会の技術に注目し、そのことによって労働という苦しみが生まれたというのです。
貯えることのできない社会では、権力者は発生しません。つまり貯えることによって権力者が発生し、多くの者が労働の苦しみを味あわなければならなかったということを物語っているのです。
古宇利島でも性交の話が出ていますが、人間の性交と出産が結びついて考えられるようになったのは、穀物栽培の社会からだとされています。「とうもろこしおばあさん」では、産む性である女性性に注目が払われ、産む性が神格化され、神である女性が犠牲に捧げられることで、穀物の豊穣がもたらされるということを語っています。
つまり農耕牧畜社会においては、家畜化された動物や栽培種化された穀物は、スピリチュアルなものから選別されて神となり、その神を殺害することによって、豊饒がもたらされます。それとともに労働の苦しみが発生するということになります。
大宇宙からの贈与は、農耕牧畜の開始によって、いったんは途絶えます。旧約聖書のアダムとイヴの楽園追放の神話は、古宇利島の神話と同類だとみてよいでしょう。古宇利島の神話は、ヘブライズム[1]における人間の原罪意識にまで拡大することができます。
キリスト教における神の子キリストの殺害は、その原罪を払拭するものとして、ジェンダーの違いはありますが、とうもろこしおばあさんと同じ位置づけにあるものとみてよいでしょう。インディアン社会とヘブライズム社会との差異は、一方は自然に敬意を払うのに対して、一方は自然をコントロールする文化を持つという違いです。
農耕牧畜社会において家族は定住生活を始めます。定住生活をしますので、狩猟採集社会におけるような家族構成員の流動性は低くなります。しかしミクロコスモスとしてマクロコスモスと対峙しなければなりませんので、コミュニティと家族は、狩猟採集社会におけるのと同様に、深く結びついたものでなければなりません。ただし定住生活の中で家族構成員の流動性は低くなりますので、家族構成の固定化が始まります。その固定化とともに親と子のあいだに支配・被支配の関係性が発生します。
3. 近代産業社会における家族
近代産業社会においては、人間は自然をコントロールするようになります。自然界の持つスピリチュアリティは脱魔術化され、科学の分析対象となり、コントロールされるものとなります。それとともに自然界の持つスピリチュアリティは貨幣に姿を変え、人間界を流通することになります。あらゆることがらが計算により支配されることになります。
人間の関係性においても、主従関係や雇用関係を確立するために、魔術的な手段にたよる必要はありません。技術的な手段と計算がそのかわりの役割を果たします[2]。モノを介してのスピリチュアルなコミュニケーション、つまり経済活動は、貨幣の流通によって代替されることになります。
スピリチュアルな価値が貨幣に換算されるようになると、貨幣は無制限に自己増殖を始めることになります。スピリチュアリティの脱魔術化によって、経済活動は大宇宙との双方向性を失い、無制限の自己増殖を目的化してしまうのです。
近代産業社会における家族は、小宇宙であるコミュニティとの絆から解放されます。大宇宙のスピリチュアルティが脱魔術化されるなかで、家族はコミュニティに守られる必要はなくなります。大宇宙のスピリチュアルティが支配していた社会では、家族と大宇宙とのあいだにはコミュニティという小宇宙が必要とされました。コミュニティが敷居となることで、大宇宙と交信するとともに、すべてのものを自然に(無に)帰してしまうという大宇宙の持つ巨大な力を制限することができたのです。
しかし自然界の持つスピリチュアリティが脱魔術化され、科学によってコントロールされるものになると、家族を守るものとしてのコミュニティの機能も、合理性を阻む固陋(ころう)なものとみなされるようになり、その価値が否定されるようになります。そのことによって近代家族は、個人と家族が強固に結びつく家族形態となったのです。
4. 生産型社会から消費型社会への移行
しかし近代産業社会はある一定の水準に達すると、生産型社会から消費型社会へ移行します。消費型社会とは社会において生産の現場が見えなくなり、生産の場と消費の場が分離される社会のことをいいます。そのような社会において家族は、消費の場として機能します。
このように生産の現場が見えなくなり、消費の場しか見えないという社会構造は、経済活動としては狩猟採集社会と類似するかもしれません。狩猟採集社会は経済活動において、生産する社会ではなく消費する社会だったからです。狩猟採集社会において生産は自然がします。人間は自然が与えてくれた恵みを消費するだけの存在だったのです。ただしその消費には、自然への感謝がありました。感謝することにより自然は、人間に恵みを与え続けたのです。
消費型社会においては消費が生産を決定します。クオリティの高い消費が生産を安定させ、生産を持続的なものにすることができるからです。消費行動が低価格なものを求める方向を志向すれば、デフレスパイラル[3]を引き起こします。このデフレスパイラルを食い止めるためには、消費者の収入が安定していること、消費者が低価格なものではなくクオリティの高い商品を求める消費活動をすることです。
企業にとっては労働者の低賃金化、消費者にとっては低価格な商品を求めることは経済合理的な行動ですが、消費型社会においてはその経済合理性がデフレスパイラルを引き起こすということです。企業が労働者のリストラや賃金カットを我慢し、消費者が同じ商品であればクオリティの高い高価な商品を購入することにより、デフレスパイラルは止まり、景気は回復に向かいます。しかしそのためには経済合理性とは異なる価値観をもたなければなりません。
企業が労働者のリストラや賃金カットを我慢するということは、企業収益を労働者に分かち合うということを意味します。消費者が乏しい家計の中からクオリティの高い商品を購入するということは、蓄えることを放棄して、陳腐化することのないクオリティの高い商品で持続可能な生活を送ることを意味します。この分かち合うこと、蓄えないことという経済活動は、構造としては狩猟採集社会の経済活動と同じです。
消費型社会であった狩猟採集社会では、自然の恵みの分配に細心の配慮がなされました。富が偏ることなく、コミュニティの全員に行き渡るように様々なタブーが設けられていたのです。
たとえば南米インディアンの中には、狩人は自分が倒した獲物は自分が食べてはいけないというタブーのある社会があります。狩人に与えられるのは名誉だけで、本人は自分が倒した獲物は食べることができず、ほかの狩人が倒した獲物しか食べることができないのです。
アチェ〔南米パラグアイ南東部のブラジル国境近くに住む民族〕の狩人には、自分が捕えた獲物を消費することを厳しく禁ずる食物禁忌が課せられている。すなわち、「殺した獣を、自ら食べてはならない」のだ。したがって、男は野営地に戻ると、獲物を家族(妻と子供達)そしてバンドの他の成員に分ける。ところが、既にふれた通り獲物はグアヤキの食料の中でもっとも重要な位置をしめている。したがって、男はそれぞれ、一生の間他人のために狩りを行ない、自分自身の食料を他人から受けとることになる。(クラストル『国家に抗する社会』)
大変不自由なタブーのように感じられますが、そのことによって狩人の個人的な技量の差による富の偏りはなくなり、結果的に獲物はコミュニティの全員にとどこおりなく行き渡るようになるのです。つまりそのようなタブーをもうけることにより、相互依存的な社会をつくりだしているのです。
消費型社会への移行により、近代家族も、富の自己増殖活動のために家族が凝集する必要性は低くなってきました。そこでは新たな家族形態が求められます。
近代産業社会が消費型社会へ移行した現代において、狩猟採集社会や農耕牧畜社会のような持続可能な安定的な社会を形成するために、新たな社会観が求められます。消費型社会への移行期にマルセル・モースの『贈与論』が再評価されたのは、そのような新たな社会観への手がかりを求めてのことだっただろうと思われます。
5. モースの贈与論
モースは贈与論において、贈与には返礼が義務づけられているのだと指摘します。そのシステムは物(マテリアリティ)と霊(スピリチュアリティ)を切り離すことなく、物には霊が込められているという物と霊との二重性によって作動します。モースは物と霊によるそのシステムをニュージーランドのマオリ族の言葉から解き明かします。
物の霊、特に森の霊や森の獲物である「ハウ(hau)」について、エルンスト・ベストのマオリ族の優れたインフォーマント(情報提供者)の一人、タマティ・ラナイピリが、全く偶然に、何の先入観もなしに、この問題を解く鍵をわれわれに与えている。「私はハウについてお話しします。ハウは吹いている風ではありません。全くそのようなものではないのです。仮にあなたがある品物(タオンガ)を所有していて、それを私にくれたとしましょう。あなたはそれを代価なしにくれたとします。私たちはそれを売買したのではありません。そこで私がしばらく後にその品を第三者に譲ったとします。そしてその人はそのお返し(「ウトゥ(utu)」)として、何かの品(タオンガ)を私にくれます。ところで、彼が私にくれたタオンガは、私が始めにあなたから貰い、次いで彼に与えたタオンガの霊(ハウ)なのです。(あなたのところから来た)タオンガによって私が(彼から)受け取ったタオンガを、私はあなたにお返ししなければなりません。私としましては、これらのタオンガが望ましいもの(rawe)であっても、望ましくないもの(kino)であっても、それをしまっておくのは正しい(tika)とは言えません。私はそれをあなたにお返ししなければならないのです。それはあなたが私にくれたタオンガのハウだからです。この二つ目のタオンガを持ち続けると、私には何か悪いことがおこり、死ぬことになるでしょう。このようなものがハウ、個人の所有物のハウ、タオンガのハウ、森のハウなのです。Kati ena(この問題についてはもう十分です)」。(マルセル・モース(吉田禎吾・江川純一訳)『贈与論』)
これを図式化すると、タオンガは品物です。タオンガはAからB、さらにCへと贈与されます。贈与に対する返礼である別のタオンガは、逆コースをたどってCからB、さらにAへと返されます。ある品物がA→B→Cと所有者を変えるのに対して、返礼である別の品物はC→B→Aと所有者を変えます。AとBとのやりとりだけでしたら、さほどむつかしい問題ではありません。贈り物に対して返礼があるだけなのです。しかし第三者であるCがこの贈与交換のリンクに入ると、問題はややこしくなります。CとAは直接の贈与交換の相手ではありません。それなのにCも贈与交換のリンクに入ってくるのです。
その謎を解く鍵は、タオンガの霊であるハウにあります。ハウは森の霊とされていますので、異界からもたらされたものだということができます。そして個人の所有物やタオンガなども同じハウとされています。つまりすべての物には、異界からもたらされたハウが憑いているものとされているのです。物の贈与は、同時にハウの贈与でもあるわけです。ハウは森の霊ですので、ハウをとどめておくことは不吉なこととされます。
ですからハウは別な品物に載せて元の所有者に返さなければならないのです。モースは品物の流れとは逆行するハウの流れを、ハウが帰りたがっているのだとしています。「要するに、ハウは生まれたところ、森やクランの聖地、あるいはその所有者のもとへ帰りたがるのである」(モース)。
ハウが異界からもたらされた霊であり、物自体は消滅してもハウ自体は消滅させられることはないので、ハウはどこまでも贈与交換によって人間関係を延長させます。そしてハウが森の霊であるかぎりにおいて、返礼は必ずなされなければならないのです。もし返礼を怠る場合には、ハウは返礼を怠るものを死に至らしめることになるのです。
ハウを大宇宙からもたらされた霊的な富であり、タオンガを人間どうしの小宇宙での富とした場合、小宇宙の富を司るものは大宇宙からもたらされた霊だということができます。そして大宇宙からもたらされた霊は、小宇宙での富を停滞させることを好みません。小宇宙での富は循環しなければなりません。さもないと大宇宙の霊から手痛い報いを受けることになるのです。
6. 人間どうしの贈与交換
この贈与と返礼のシステムを、モースは、人間どうしの贈与交換と人間と異界=他界との贈与交換に分けて分析しています。
人間どうしの贈与交換は、現在においても社会の土台をなしていますが、もっとも端的な例は家族に求めることができるでしょう。家族ほど市場的売買交換にふさわしくないものはありません。親から子へ、祖父母から孫へ、一方的な贈与がなされるのは当然のこととされています。
贈与の返礼は、家族的な情愛です。この大きな贈与のサイクルが、家族を成立させているのだといってもよいでしょう。イエが制度化されると返礼は親孝行として義務化されます。しかし人類史的には、親孝行などのような返礼を求める家族形態は例外に属するものだといえるでしょう。それは永続するイエという意識が発生することによって起こります。
永続するイエ意識が成立していない社会においては、家族は返礼を求めることのない一方的な贈与関係によって形成されています。贈与に対する返礼を求めない、あるいは贈与した本人に対する返礼をことさらおこなわないということにより、家族という不思議なコミュニティは、「帰る場所」としての宇宙論的意義をもつことになるのです。
これは後で詳述しますが、贈与の一方的な流れこそが、むしろ形を変えた大きな返礼になるということが、家族という不思議なコミュニティの意味するところだとおもわれます。
人間どうしの贈与交換について重要なことは、贈与に対してただちに返礼が求められるという点にはありません。贈与に対する返礼が遅れることに価値が置かれるという点にあります。贈与に対して時間をおかずに返礼があった場合、贈与によって確保された信頼関係も、底の浅いものとなってしまいます。
贈与に対する返礼は、時間をかければかけるほど、信頼関係は保たれることになります。それも同じ人間どうしのやりとりではなく、次々に異なる人に贈与がなされ、それが最終的に贈与する本人に帰ってくるならば、多くの人を介在した分だけ、贈与の価値は増すことになります。
宗教学者の中沢新一は、贈り物をもらって、それに即座にお返しをするのは失礼なことだとしています。
贈り物をもらって、それに即座にお返しをするのは失礼なことですし、また同じ価値をもったモノを返礼にすることはできません。贈り物はいただいてしばらく時間がたってから、おもむろに返礼はなされなければなりません。交換の場合ですと、商品とその対価はできるだけ間をおかずに交換されなければなりませんが、贈与では、返礼は長い時間間隔をおいてから返ってきたほうが、友情や信頼が持続していることの証拠として、むしろ礼儀正しいことだと感じられるのです。(中沢新一『愛と経済のロゴス』)
日本のことわざに「情けは人のためならず」という言葉がありますが、これは情けをかけるのは他人のためではない、他人にかけた情けは巡り巡って必ず自分のところに戻ってくるのだ、ということをあらわしています。そして多くの人の善意がくり返されることによって戻ってくる情けは、信頼関係の増幅であり、遅延された分だけ価値が高められているということをあらわしているのです。
7. 異界や他界との贈与交換
二つ目の贈与交換は、異界や他界との贈与交換です。異界や他界は大宇宙(マクロコスモス)とみなされ、個人や家族、共同体は、その大宇宙に包まれた小宇宙(ミクロコスモス)とみなされていました。沖縄のことわざに「グソーヤアミデー」というものがあります。
グソーというのは後生のことで、他界を指します。アミデーというのは雨垂れ、つまり雨垂れする軒下のことをあらわします。このことわざの意味は、「あの世の人は雨戸のすぐ外だよ」ということです。死者はすぐ間近に存在しているということです。このことわざにみられるように、一歩外に出ると、そこは異界や他界である大宇宙の領域だったのです。
人間のコミュニティという小宇宙は、異界や他界という大宇宙に包まれていました。そのため異界や他界との贈与交換は、人間どうしの贈与交換以上に重要なこととされていました。富は異界や他界に存在するものとみなされ、異界や他界との贈与交換によって富は人間の世界にもたらされるものとされていたのです。
昔話や伝説を振り返ると、富は異界や他界にあるとされる説話が普遍的です。幸運な者だけがそれを手に入れることができるのですが、その幸運な者は努力して富を手に入れるのではありません。異界や他界の目にかなうものだけが幸運を手に入れることができるのです。歴史学者の阿部謹也は、このような説話の世界を「小宇宙から大宇宙を垣間見る所で成立したもの」だとしています。
私は、グリムのメルヘンはほとんど例外なしに小宇宙から大宇宙を垣間見る所で成立したものだという風に考えています。なぜかと言うとメルヘンの主人公は基本的にはひとり旅ですね。メルヘンの主人公はひとりで旅をし、そして必ずどこかで救い手が現れています。彼を助ける人というのは全部大宇宙から来る。妖精とか植物とか動物とかですね。決して人間、仲間の人間ではないんですね。大宇宙から来るんです。そして彼は、別れ道に来ても一切迷うことはなく、必ず右か左にぱっと進むのです。また、難問を課されても少しも苦しむことがない。誰か必ず助け手が現れてすべての難問は解決されるんですね。そしてもう少し考えれば、メルヘンの主人公には内面性というものがない。あるいは内面的な葛藤というものがないんですね。(阿部謹也『中世賤民の宇宙』)
「メルヘンの主人公には内面性というものがない」という指摘は重要です。近代的知の枠組みでは常に内面的な葛藤が物語の主題となりました。私とは何者なのかという問いが重要視されたのです。私という個人が関係性によって創られたものであるならば、その内側をいくら覗き込んでも答えは見つかりません。むしろ社会的関係性の網の目の一端が私という個人であるという認識に立たなければ答えは見つかることはないのです。
自助グループにおける「言いっ放し、聞きっ放し」というコミュニケーションの方法も、内面性の放棄だとみることができます。自己の内面に意味を持たせるのではなく、自己を語るという外面に意味を持たせるのです。それは誰も触れることのできない内面性を、誰でも聞くことができるという外面性に反転させる作業になります。外面性というのは見られた存在としての私です。それは単に他者に見られるという私を意味するだけではありません。
近代社会は、「われ思うゆえにわれあり」というような近代的自我を確立し、内面的な葛藤を重視しました。その結果、自己の内面を重視し、外面を軽視することになりました。外見を飾らないことが内面のクオリティを表現するものとみなしたのです。しかし近代社会以外の多くの社会では、外面によって宇宙論的秩序の中にある自己を表現しました。
近代社会においてタトゥーやピアシングは内面性がないものとみなされ、野蛮を物語るものとして排除されていきました。しかし多くの社会において、タトゥーやピアシングは、自己の身体に宇宙論的秩序を表現するものでした。そのことによって宇宙論的秩序の中にある自己を表現したのです。タトゥーやピアシングなどのような外面性による自己表現は、大宇宙の一部である自己を表現していたといえるのです。つまり内面性ではなく外面性によって、人間は大宇宙の秩序とつながることができたのです。ですから「一切迷うこと」がないのです。
アディクションはスピリチュアルな病であるという言い方がなされます。それは近代社会から排除されたスピリチュアリティを感じることによって、はじめて「内面的孤独化の感情」(ウェーバー)から解放され、回復に向かうことができる病気であるからといえるでしょう。
大宇宙との贈与交換で、もう一つ重要なことがあります。それは生と死です。ハウとタオンガの関係は、人間の霊と肉体においても同じ構図でとらえられました。森の霊であるハウは肉体としてのタオンガとして生誕します。そしてハウは大宇宙である森へ帰りたがります。ハウが小宇宙へ出現するとき、そして大宇宙へ帰還するとき、大宇宙と小宇宙との通路が開かれます。そのときに大宇宙との贈与交換がおこなわれるのです。生誕も死も異界や他界の富をもたらす機会であったのです。
AAにおいても「霊的な目覚め」が重視されましたが、その霊性はハウだということができます。タオンガとハウの二重性により、贈与交換のシステムは作動するのですが、霊的に目覚めるということは、自己をタオンガとして所有するのではなく、ハウとして贈与交換のリンクのなかに投げ入れることを意味します。
8. 贈与交換と家族
家族は贈与交換のリンクにおいて、返礼の義務がともなうことのない、一方的な贈与の流れがあるだけのもっともピュアな形態であるということができるでしょう。通常、親から子への贈与、祖父母から孫への贈与などには、返礼は期待されません。返礼が期待されるとなると、それは家族という関係性ではなく、支配・被支配という関係性になります。そのような関係性の家族があるとしても、それは病んでいる家族関係だといえるでしょう。
モースの『贈与論』の題字にスカンディナビアの古代神話伝説詩『エッダ』が引用されていますが、その一節に「贈り物には贈り物を返さなければならない」という贈与に対する返礼の義務がうたわれています。
たとえば沖縄では、採れたての野菜などをいただいた場合、その野菜を入れていた笊を空のままで返してはいけないということがいわれていました。どんなものでもよいから、笊に何かを入れて笊を返さなければならないとされていたのです。この風習などは、とりあえずの返礼だということができるでしょう。
しかし贈与にともなう返礼は、遅延されるほど価値を増すものとされています。ハウを恐れるだけではなく、ハウが小宇宙を循環することにより、大宇宙との連続性がもたらされてくるのです。その遅延される返礼は家族において端的にあらわれます。
コミュニティ内における贈与には返礼する義務がともないます。しかし家族内における贈与には返礼の義務がともなうというイメージはありません。親から子へ、子から孫へと一方的な贈与の流れがあるだけのようにみえます。ここに他の贈与交換と家族における贈与交換の違いが認められます。その秘密は反復にあるような気がします。反復とは何かというと、生育のやり直しです。
私という人間は家族によって成育されますが、言語を習得する以前の生育の過程を自覚することはできません。ただ一方的な贈与を受けるだけです。私に子どもが生まれるとすると、私は子どもを養育しますが、そこで反復されるのは、私を養育した親の育児体験を追体験することです。しかし私の子どもがさらに子どもをつくり、私の子どもが私にとって孫に当たる人間を養育する段階に至ると、私は養育される私の体験を、孫を通して追体験することになります。つまり孫を通して言語習得以前の自分の生育の過程を反復することになります。
このような言語習得以前の生育過程の反復は、家族においてしかなされません。そこに家族という小さなコミュニティの必要性があるのだと思われます。贈与に対する返礼は、行為としては無いように見えるのですが、実は孫を通して自分の成育過程を反復することによって、子どもから返礼を受けているのだとみることができるでしょう。孫は祖父母である「私」の反復した姿です。親が子を愛するならば、それは「子」の姿で反復される「私」への返礼になるのです。
わかりやすく血縁関係の言葉で説明しましたが、この家族的な贈与の流れは、血縁関係である必要もありません。極論をいえば、世界の赤ん坊のすべては、言語獲得以前の「私」の反復する姿なのです。ですから世界のすべての赤ん坊が幸せであることが、そのまま「私」が愛される存在であり、幸せであることにつながるのです。
これを図式であらわしますと、贈与の流れは、A→B→A”という流れになります。A”というのは、孫であるとともに、自己の生育過程の反復を意味します。一方的な贈与の流れが、実は形を変えた返礼であるということになります。この一方的な贈与の流れこそが、家族を他の人間コミュニティとは異なる次元のものにしているのだということができます。
一方的な贈与の流れは、大宇宙から小宇宙へなされるものです。家族はその意味において宇宙論的な意義を有するコミュニティだということができるでしょう。ハウが大宇宙に帰りたがる性質をもつように、家族も大宇宙とのハウの循環のなかで、帰るべき場所となるのです。
親孝行というイデオロギーや近代家族における「爆発的な親密性」は、ハウの流れを滞留させるものだということができるでしょう。
親孝行イデオロギーにおいては、親から受けた贈与を、ただちに返礼として親に返さなければなりません。近代家族においては親の期待値に応えなければならないという、ただちにされる返礼が求められます。その関係性は、家族を開放系から閉鎖系へと変換させてしまいます。ハウの流れが、A→B→A”から、A→B→Aへと変わるのです。
そのような関係性においては、ハウの大宇宙から小宇宙へと循環する流れが止まりますので、家族は「帰る場所」であるとともに「自分を引き篭もらせる場所」ともなるのです。
9. まとめに
近代産業社会は、富が無制限に自己増殖を繰り返すという近代資本主義の社会でした。富の無制限な自己増殖にあわせて、家族はコミュニティから引き篭もりを開始します。コミュニティは無制限の拡大を好まず、家族をコミュニティの一員として限定づけようとします。そのため家族とコミュニティが分離していくのです。
そのコミュニティと家族の分離を可能にしたのが、女性の家族への囲い込みでした。女性を家族に囲い込むことによって、コミュニティの持つ相互扶助機能を女性に肩代わりさせたのです。無制限に富の自己増殖を繰り返す近代資本主義社会において、無制限に能力を伸ばす可能性を持つものは子どもでした。そのため子どもは学校と子供部屋に囲い込まれ、親の期待を果たす存在となります。
そのような近代家族の成立が可能であったのは、資本主義社会が生産型社会であったときです。資本主義社会が一定の発達段階に達し、消費型社会に移行すると、女性と子どもを家族に囲い込む近代家族の形態は、維持することができなくなります。
消費型社会に移行するとともに昇給の伸びは鈍化し、管理職ポストも増やすことができなくなります。昇給の伸びが鈍化すると、男性は女性を家族に囲い込むだけの収入が得られなくなります。管理職ポストが増加しないことは、子どもが親の期待に応えることができなくなることを意味します。①昇給の伸びが鈍化すること、②子どもが親の期待する職業ポストに就けなくなること、というこの二つの要因により、近代家族はその成立基盤が揺らいできます。
家族形態と産業構造と宗教形態は、常に三位一体で変化していきます。産業構造が生産型社会から消費型社会へ移行したとき、家族形態、宗教形態ともに、産業構造にあわせて変化しなければなりません。そこではどのような変化が予期されるでしょうか。
消費型社会が企業収益の労働者へのシェア(分かち合い)や消費行動におけるクオリティの高さに求められるならば、それに類似する社会は狩猟採集社会だということができるでしょう。狩猟採集社会においても、獲物のシェアや獲物に対する敬意に満ちあふれていたからです。
生産型社会では企業が収益を蓄積して企業規模を拡大し、家族が財産を獲得するのは、社会的な共通利益となっていました。しかし消費型社会へ移行するともに、産業社会において共通利益とされていたものが、社会的停滞の元凶となってしまいました。企業収益の確保が労働者のリストラや賃金カットによって果たされ、家族の財産維持が消費の抑制によってなされていくようになるからです。
消費型社会においては、企業活動も家族形態も変化していかなければなりません。そのためには宗教形態の変化も必要とされます。近代産業社会が宗教の脱魔術化によってスピリチュアルなものを排斥したのに対して、スピリチュアルなものの回復が必要とされます。なぜならば消費型社会は、「消費が生産を決定する」社会ですので、生産と消費の関係性が生産型社会と逆転しなければなりません。
その逆転を可能にするのが、商品にともなうスピリチュアリティです。そのスピリチュアリティによって消費者と生産者が結ばれます。そのことによって消費者と生産者の双方に満足を与えるクオリティの高い商品の生産が可能となるのです。生産型社会が商品からスピリチュアリティを排除することによって成立したのに反し、消費型社会では商品にスピリチュアリティを込めることにより、生産が成立するのです。
家族も「帰る場所」としての家族形態が求められるでしょう。そこには生命科学や財産の維持管理によって定義される家族像だけではなく、スピリチュアルなものが必要とされるものとおもわれます。スピリチュアルなものを介在させることによって、家族はコミュニティに開かれることが可能となるのではないでしょうか。
参考文献
クラストル「国家に抗する社会』(1989年、水声社)
マルセル・モース『贈与論』(2009年、ちくま学芸文庫)
中沢新一『愛と経済のロゴス』(2003年、講談社選書メチエ)
[1] 古代ユダヤ教から発生した文化のこと。キリスト教やイスラム教もそれに含まれる。
[2] マックス・ウェーバー(岡部拓也 訳)『職業としての科学』
[3] デフレーション(Deflation)と、スパイラル(Spiral=螺旋)を掛け合わせた言葉。物価の下落と実体経済の縮小とが、相互に作用して、らせん階段を下りるようにどんどん下降していくこと。物価の下落が継続して起こり、それにつれて景気がどんどん悪くなる状況をさす。物価下落→企業の売上の減少→企業収益の滅少(売上が減少したにもかかわらず、賃金などは短期的にはすぐに下がらないため)→企業行動の慎重化=設備投資や雇用の調整→個人消費などの最終需要の滅少→さらなる物価下落
家族
モースの贈与論
モースの贈与論
マルセル・モース(1872–1950、フランス)は『贈与論』(1925)において、贈与には返礼が義務づけられているのだと指摘します。そのシステムは物と霊との二重性によって作動します。モースは物と霊によるそのシステムをニュージーランド・マオリ族の言葉から解き明かします。
物の霊、特に森の霊や森の獲物である「ハウ(hau)」について、エルンスト・ベストのマオリ族の優れたインフォーマント(情報提供者)の一人、タマティ・ラナイピリが、全く偶然に、何の先入観もなしに、この問題を解く鍵をわれわれに与えている。「私はハウについてお話しします。ハウは吹いている風ではありません。全くそのようなものではないのです。仮にあなたがある品物(タオンガ)を所有していて、それを私にくれたとしましょう。あなたはそれを代価なしにくれたとします。私たちはそれを売買したのではありません。そこで私がしばらく後にその品を第三者に譲ったとします。そしてその人はそのお返し(「ウトゥ(utu)」)として、何かの品(タオンガ)を私にくれます。ところで、彼が私にくれたタオンガは、私が始めにあなたから貰い、次いで彼に与えたタオンガの霊(ハウ)なのです。(あなたのところから来た)タオンガによって私が(彼から)受け取ったタオンガを、私はあなたにお返ししなければなりません。私としましては、これらのタオンガが望ましいもの(rawe)であっても、望ましくないもの(kino)であっても、それをしまっておくのは正しい(tika)とは言えません。私はそれをあなたにお返ししなければならないのです。それはあなたが私にくれたタオンガのハウだからです。この二つ目のタオンガを持ち続けると、私には何か悪いことがおこり、死ぬことになるでしょう。このようなものがハウ、個人の所有物のハウ、タオンガのハウ、森のハウなのです。Kati ena(この問題についてはもう十分です)」。(マルセル・モース(吉田禎吾・江川純一訳)『贈与論』)
これを図式化すると、タオンガは品物です。タオンガはAからB、さらにCへと贈与されます。贈与に対する返礼である別のタオンガは、逆コースをたどってCからB、さらにAへと返されます。ある品物がA→B→Cと所有者を変えるのに対して、返礼である品物はC→B→Aと所有者を変えます。AとBとのやりとりだけでしたら、さほどむつかしい問題ではありません。贈り物に対して返礼があるだけなのです。しかし第三者であるCがこの贈与交換のリンクに入ると、問題はややこしくなります。CとAは直接の贈与交換の相手ではありません。それなのにCも贈与交換のリンクに入ってくるのです。
その謎を解く鍵は、タオンガの霊であるハウにあります。ハウは森の霊とされていますので、異界からもたらされたものだということができます。そして個人の所有物やタオンガなども同じハウとされています。つまりすべての物には、異界からもたらされたハウが憑いているものとされているのです。ですから物の贈与は、同時にハウの贈与でもあるわけです。ハウは森の霊ですので、ハウをとどめておくことは不吉なこととされます。ですからハウは別な品物に載せて元の所有者に返さなければならないのです。モースは品物の流れとは逆行するハウの流れを、ハウが帰りたがっているのだとしています。「要するに、ハウは生まれたところ、森やクランの聖地、あるいはその所有者のもとへ帰りたがるのである(モース前掲書36ページ)。
ハウが異界からもたらされた霊であり、物自体は消滅してもハウ自体は消滅させられることはないので、ハウはどこまでも贈与交換によって人間関係を延長させます。そしてハウが森の霊であるかぎりにおいて、返礼は必ずなされなければならないのです。もし返礼を怠る場合には、ハウは返礼を怠るものを死に至らしめることになるのです。
ハウを大宇宙からもたらされた富、タオンガを人間どうしの小宇宙での富とした場合、小宇宙の富を司るものは大宇宙からもたらされた霊だということができます。そして大宇宙からもたらされた霊は、小宇宙での富を停滞させることを好みません。小宇宙での富は循環しなければなりません。さもないと大宇宙の霊から手痛い報いを受けることになるのです。

イラストは『社会学用語図鑑』(2019年、プレジデント社)












