ヘアーインディアンと家族
- 1. さまざまな家族が語られ始めた
- 2. ヘアー・インディアン
- 3. 世帯という概念の成立しない社会
- 4. 個人を中心とした社会
- 5. 流動的な夫婦関係
- 6. 流動的な親子関係
- 7. 父親は社会的な父親
- 8. ミウチ
- 9. まとめに
1. さまざまな家族が語られ始めた
共時的に家族は、多様化いていることが指摘されてきました。未婚独身、結婚しない異性との同棲、子どもをもたない夫婦、ひとり親家族、離婚独身、ステップ・ファミリー、共働き家族、伝統的核家族、単婚にこだわらない夫婦(合意による婚外の性関係)、別居家族、同性同士のカップル、友人コミュニティ、伝統的三世代同居、二世帯型同居、高齢者独居(寡婦・寡夫)、一夫一婦婚、一夫多妻婚、一妻多夫婚、結婚をしない家族、ペットを含む家族などというように。
(共時的:言語学者ソシュールの用語。時間の流れや歴史的な変化を考慮せず、一定時期における現象・構造について記述するさま)
現在の家族社会学の研究では、家族を定義するのはむつかしいとされています。それは「家族なるもの(The Family)」の意味するものが、通時的には異なった内容を意味するものであり、共時的には多種多様な形態をとるものであるからです。
(通時的:言語学者ソシュールの用語。関連する複数の現象や体系を、時間の流れや歴史的な変化にそって記述するさま)
ヨーロッパにおいてThe Familyは、通時的にいうと、長い間、一人の家父長の下で生活を共にする、親子や血縁者、使用人や徒弟などの非血縁者までも含む言葉として使用されていました。17世紀から18世紀にかけて、The Familyという言葉の意味するものが、見返りを求めない情緒と私的な事柄(プライバシー)という新たに登場した意味と結びつき、親子関係からなる核家族を意味するものに変化していきます。
家族を定義するのはむつかしいのですが、家族は「現実の家庭環境がどうであれ、すべての人間は『家族的存在』であるほかはない」(斎藤環『家族の痕跡』)存在であるともいえます。
そこで今回の講義では、さまざまな家族が語られてきたことを受けて、原ひろ子著『ヘヤー・インディアンとその世界』(1989年、平凡社)を主軸にして、家族を考えてみたいと思います。
2. ヘアー・インディアン
ヘヤー・インディアンとはカナダの北極圏に先住し、インディアン中で最北部に住む部族です。人口は300人から500人(1960年代当時)で、約9万平方キロ(日本の本州の四分の一弱)の地域に住み、少グループに分かれて分散してキャンプし、食料を求めて常にテントの移動を余儀なくされています。
主な食料は野ウサギで、そこからヘヤーhare(野ウサギ)という名称がついています。(現在はカナダ政府の同化政策によって伝統的な生活は消滅しつつあると言われています)

広大な極北圏で猟をするヘヤー・インディアンは、定住することなく一年のほとんどをテント小屋で暮らします。ところがテント小屋のメンバーは流動的で一定することはありません。そのような流動的なテント・メンバーの生活の中で重視されるのが、インセスト・タブーです。子どもが生まれると、必ず誰が父親であるのかが決定されます。そのことによって、インセスト・タブーとされる人間関係が決定されるのです。このインセスト・タブーを守ることによって、ヘヤー・インディアンのコミュニティは成立します。
ヘヤー・インディアンは徹底して個人主義的であり、男女のカップルは、あくまでも気の会うものどうしのカップルであり、育児は楽しみの一つとされ、生物学的な母親にということではなく、育てることのできる者が子どもを育てるということが基本の社会です。
現在の資本主義経済における先進諸国の家族は、欧米諸国でここ30年(1980‐2008年)ほどで婚外子割合が急増するなど、劇的な変化を遂げつつあります。
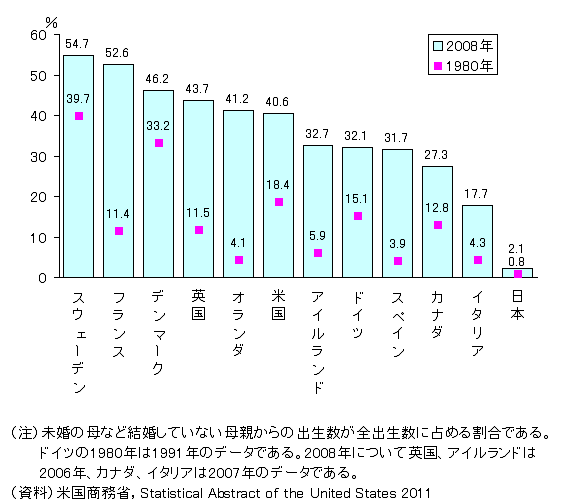
それは、結婚制度による結婚よりも、カップルでいることを重視する社会に変化しつつあることを意味するのだといえるでしょう。
このように結婚制度によらない、気の合った者どうしがカップルをつくるという社会が、「未開」と呼ばれる社会にもありました。それは文化人類学者の原ひろ子(1934‐2019)が、1961年から63年にかけてフィールド・ワークした、ヘヤー・インディアンの社会です。
3. 世帯という概念の成立しない社会
そこで彼女が発見したのは、メンバーの固定した「ある程度持続的に、寝食を共にする生活集団」としての「家族」ではなく、個人を中心としたネットワーク社会でした。ヘヤー・インディアンは丸木小屋やテントで生活しますが、そのメンバーは一定することなく、流動的であり、そこには「世帯」という概念に当てはまるものはなかったのです。
丸木小屋の持ち主は、AとかQとか特定の個人だ。そして、そこをまあまあ常時利用している核になるような人びとも、だいたい決まっているのだが、すべての丸木小屋に関して、誰がいつどこに寝ているかということは、一晩単位で変動するのだということがわかってきた。特定のテントに寝る人びとが誰と誰であるかはじつに流動的なのだ。(原ひろ子『ヘヤー・インディアンとその世界』207‐208ページ)
そこで原は、世帯という概念を捨て、テントで生活を共にする一時的な居住集団を「テント仲間」と呼ぶことにします。そして、家族に当たるものを「ミウチ」とし、性生活の相手を「ツレアイ」とし、個人のパーソナリティ要因を契機とする親族ネットワークを「シンルイ」と名づけて、ヘヤー社会の人間関係を分類しました。

4. 個人を中心とした社会
ヘヤー・インディアンの社会は、徹底して個人主義的な社会であり、個人のパーソナリティを重視してネットワークが形成される社会でした。そのため集団を統合するような指揮系統が発達することは少なく、その代わりに流動的なネットワークが社会を維持するものとして機能することになります。
宗教的にはコミュニティを統合するような宗教はなく、各個人にその個人特有の守護霊があり、守護霊と個人の結びつきが、もっとも重視されます。各個人はそれぞれが守護霊を持っており、その守護霊が個人の行動を決定します。ですから徹底して個人のパーソナリティが重視されるのです。
ヘヤー・インディアンは、一人ひとりが自分の守護霊をもっている。それはビーヴァーやテンやクズリなどの動物で、一人につき一種の動物が守護霊となる。三歳ぐらいの子どもでも、「僕ね。昨夜の夢にテンが出てきて、今日はブッシュに入ってはいけないと言われたんだよ」などと口走る。すると、まわりの大人や年上の子どもたちが、「そうか、そのテンがお前をずっと守ってくれるんだよ」と決めつける。こうして順調にいけば、三、四歳以上の子どもたちがいつの間にか夢の啓示を得て、どの動物が自分の守護霊であるのかを知るのである。(同前341ページ)
ヘヤー・インディアンの社会では、一般論は成立しません。すべて守護霊と個人との霊的な交信によって決定されるからです。ですから「一人ひとりの子どもたちを独自の人格と特徴をもった個人」として見られることになります。
他者から教わるという概念も成立しません。自分で観察し、試行し、自分で修正することによって、「○○をおぼえる」ことになるのです。
テント仲間のメンバーが常に変化するのだから、特定の「家庭料理」とか、「この家庭のやり方、流儀」、「家風」というものも存在しない。技術や習慣なども、すべて個人個人のものなのである。(中略)そして、一人ひとりの人間が、「その人らしさ」をもった個人として充分に充実して生活しているのである。(同前244‐245ページ)
このように他者を一般論で見ることをせずに、個別性で見るという見方は、ネットワーク社会といわれる現代社会に通じるものがあるといえるでしょう。
5. 流動的な夫婦関係
ヘヤー・インディアンは「家族は同じ屋根の下で住むのが当然だ」という考え方が弱く、男女のカップル関係も流動的です。
テント仲間を構成する男女の対は、(中略)労働力のバランスのとれたパートナーで、気が合えばよいのだ。セックスもするけれど、相手に惚れ込んでいるかどうかということは、別の次元に属することなのだ。男も女も、個人差はあるが、一時に一人ないし七、八人の恋人をもっている。(中略)一般には、恋と日常生活は別のものである。(同前223ページ)
「男女の同棲は、あくまでも気の合っている間だけつづければいい」という気持ちが流れていることだ。したがって、「偕老同穴の契りを結ぶ」というような考え方はいっさい存在しない。(中略)つまり、西欧の近代的な夫婦の理念にみられる「二人の男女が愛情を深め合って長い年月を共に送る」ということは、ヘヤー・インディアンの男女の生活においては二義的なものなのである。(同前242ページ)
偕老同穴:夫婦が仲むつまじく添い遂げること。夫婦の契りがかたく仲むつまじいたとえ。夫婦がともにむつまじく年を重ね、死後は同じ墓に葬られる意から。▽「偕」はともにの意。「穴」は墓の穴の意。
6. 流動的な親子関係
ヘヤー・インディアンの社会は、個人を中心としたネットワーク社会なので、生みの母が子どもを育てなければならないという概念は存在しません。
「乳児は、その子を生んだ母親が育てなければならない」という我われ近代日本人の理念における大前提が、この社会には存在しない。「子どもは、育てられる者が育てればいい」のであって、「それが実の母親なら望ましいが、何も実の母に限ることはない」という考え方である。ヘヤー社会にはじつに養子や里子が多い。聞いてみると、「生まれてすぐは、父方の祖母に育てられて、隣りのテントのシンルイではない小母さんから乳をもらい、それから母の妹の所で暮して、七つのころ、一時、母親と暮したけれど、あとは母の兄の家族と暮して、今の夫と結婚した」というような話がよくある。このような西洋や日本でなら「家なき子」として悲劇の主人公になりうるようなケースが、彼らの間では決して悲劇とは考えられていないのである。(同前242‐243ページ)
ヘヤー・インディアンの社会では、育児は「遊び」と同じくらい「楽しいこと」のカテゴリーに入り、養子や里子の引き取り手に困ることはありません。「育児上の用事は、ほとんど子どもの母親そのほかの女の手によって行なわれるが、父親や男たちも、気軽に哺乳壜にミルクを調合したり、おむつを替えたり、遊んでやったりする」ということになるのです。
7. 父親は社会的な父親
人間関係、親子関係の流動的なヘヤー社会でも必ず決定しなければならないことがあります。それは誰が子どもの父親であるかということです。
彼らは、誰と誰がいつ、どこで、一緒にキャンプしていたかということに強い関心をもっている。そして、男女の性交によって妊娠し、人間の妊娠期間が280日ぐらいだということも知っている。だから、出産日から逆算して「この子の父親は、あいつだ」ということを推定し、さらに世論としての噂話や、産婦の話から、その子の父が決まることになる。(同前256ページ)
ヘヤー・インディアンは、生物学的な父親を確認しようとする必要は感じない。これに対して、社会的な父親が決まることは、母親にとっても、またヘヤー社会全体にとっても、絶対不可欠な事柄なのである。(同前257ページ)
この引用で重要な点は、父親の確定が「世論としての噂話や、産婦の話から」なされるということです。ある程度は生物学的な父親を推定するのですが、「生物学的な父親を確認しようとする必要は感じない」というのです。それでは何のために父親の確定が必要なのかというと、インセスト・タブーの範囲を確定するためです。そのため社会的な父親が決まることは、「絶対不可欠な事柄」ということになるのです。
インセスト・タブー
インセスト・タブー (Incest Taboo)とは、人間社会において、特定のカテゴリーに該当する親族との結婚や性的関係を禁じる社会的規範のことで、あらゆる社会で普遍的にみられる。
インセストは、近親婚や近親相姦と訳される。またタブーは、禁忌と訳されるように、たんに禁止というのではなく、その社会の成員すべてが規範をおかすことに強い怖れや忌(いみ)の感情をいだき、順守することが当然とうけとめているものである。
人間以外の霊長類やその他の生物種にも、母子間や兄弟・姉妹間の性行為をさける事実があることはよく知られている。しかし、こうした動物のインセストの回避とインセスト・タブーは、現在では区別してあつかわれている。それは、人間の場合にはタブーの対象となっているインセストの概念そのものが、それぞれの社会、歴史、文化によってかなりことなり、近親にかぎらず疑似的な血縁関係もふくまれるなど、恣意的(しいてき)につくられたカテゴリーといえるからである。
母と息子、父と娘、兄弟・姉妹同士の性的関係は、ほとんどの社会で禁じられており、実際には血のつながっていない養子や義理の関係にも適用されている。しかし、オジ・メイ、オバ・オイ、イトコ同士となると、インセストとみなす範囲の偏差がはげしく、母方であるか父方であるか、交叉イトコ、平行イトコなどによっても違いがある。さらに、氏族(クラン)、半族といった社会組織による外婚規制にも、インセスト・タブーの概念が入りこんでいる。(『Microsoft エンカルタ百科事典 2000』より)
それでは噂話や産婦の話によって父親を決定していいのかという疑問と、もし娘が生まれた場合、生物学的な父親と性愛する可能性があるのではないのか、それはインセスト・タブーを破ることになるのではないのかという疑問が生じます。
文化人類学者のクロード・レヴィ=ストロース(1908-2009)は、その著『親族の基本構造』(1949)において、インセスト・タブーの意味することを、男性たちに互酬規則を命じるものだと捉えました。
つまりインセスト・タブーの意味するところは、たんにインセストのカテゴリーに入った女性たちとの性愛や婚姻を禁じるものではなく、インセストのカテゴリーに入った女性たちをその帰属する集団とは異なる他の男性と交換せよ(贈与交換)、という命令だとしたのです。
つまり、インセスト・タブーは禁止を意味するだけではなく、贈与交換することによって親族という仲間をつくるための規則だといえます。インセスト・タブーが贈与交換の規則であるならば、父親の意味するところは生物学的なものだけではなく、社会関係を成立させるための社会的存在であるということになるのです。
贈与交換とはマルセル・モースの『贈与論』(1923-24=1943)で論じられた概念で、贈与と返礼の交換が社会を存続させる重要な役割を担っているという理論で、レヴィ=ストロースの提唱する構造主義に大きな影響を与えました。
父親という存在がなぜこのようにややこしいのかというと、父親というのは人類にしか存在しない社会的存在であるからです。霊長類研究のサル学では、父親という存在は、ヒトが誕生したと同時に生成した社会的存在であるとします。
サル社会には、父親は存在しない。父親というのは、家族という社会的単位ができる、つまり、ヒトが誕生したと同時に生成した社会的存在である。ということは、父親は家族の成立に伴って創り出されたものであり、極言すれば発明されたものなのだ。一方、母親は生物学的存在であるとともに社会的存在だ、という二面性を持っているのである。(河合雅雄『子どもと自然』178ページ)
レヴィ=ストロースによると、インセスト・タブーによって家族やコミュニティという社会単位が誕生し、同時に人間という文化的な存在も誕生することになります。父親という存在も人間が誕生すると同時に、生成されることになるのです。インセスト・タブーを破ったならば家族もコミュニティも形成されず、人間でもなくなります。そういう社会では父親は存在しないのです。
8. ミウチ
社会的父親が決定されなければならない最大の理由は、インセスト・タブーです。インセスト・タブーの守るべき範囲を設定するために、社会的父親が決定されなければならないのです。
人間関係が流動的なヘヤー社会でも、父、母、父母をともにするキョウダイ、ツレアイ(性生活の相手)とその間の子どもに対しては、ツレアイを除いて、これらの人びとと性交渉をもってはいけないというタブーがあります。このタブーのために、社会的父親が決定されなければならないのです。父親が確定されることによって、父母をともにするキョウダイが確定することになり、同父母キョウダイは、インセスト・タブーの対象となります。つまりインセスト・タブーの範囲を確定するために、社会的父親の決定が「絶対不可欠な事柄」になるのです。
原は、このようなインセスト・タブーの範囲内にある人びとを、「ミウチ」という言葉でカテゴリー化します。
ヘヤー・インディアンの「ミウチ」は、幾重にも張り巡らされたタブーによって、運命を共にする相互関係をもつことになります。しかし、「ミウチ」のカテゴリーに該当する人びとが、「我われ意識」をもつことはないとされます。一人ひとりが個人的に、もろもろのタブーに「ミウチ」として拘束されるだけなのです。
ヘヤー・インディアンの「ミウチ」は、一つのテントで寝食を共にすることによって、生活共同体を形成しているのではない。しかし、超自然的に規定されたタブーの存在によって、運命を共にする相互関係をもつのである。(中略)しかし、ヘヤー・インディアンの考え方によると、特定個人(A)の「ミウチ」のカテゴリーに該当する人びとが、「我われAのミウチに当たる者ども云々」といった、「我われ意識」をもつことはないのである。彼らの一人ひとりがそれぞれ常に、「私はAとミウチだから」ということを意識して行動しているに過ぎない。((原ひろ子『ヘヤー・インディアンとその世界』268ページ)
ヘヤー・インディアンにおける「ミウチ」は、家族の究極の形態を示すものだといえるでしょう。「ミウチ」はインセスト・タブーとそれにともなうさまざまなタブーを共有するだけであり、そこには「我われ意識」は存在しないのです。つまり、家族の究極の姿は、インセスト・タブーを協約する関係性そのものになってしまうのです。
9. まとめに
人類は贈与交換を行なうことによって社会を形成してきました。そして女性の贈与交換を行なうことによって、親族を形成し、家族を形成してきました。この親族からコミュニティが形成されることになります。
女性の贈与交換ということの根底にあるのはインセスト・タブーです。インセスト・タブーは、精神分析における無意識のように、親族=コミュニティをつくるようにと命令する視えない構造だということができます。この視えない構造によって、家族が形成されるのだといえるでしょう。つまり、コミュニティと家族は、分離できないものとして同時に生成されたものだといえるのです。
近代家族は、家族をコミュニティから分離させることによって誕生しました。家族がコミュニティと不可分な存在であるとすると、家族にとってコミュニティとは何であるのかが、再び問われることになるでしょう。そして近代家族が個人主義的にならざるを得ないものだとすると、ヘヤー・インディアンにおける個人の守護霊に代わるものが何であるのかが、問われなければならないといえるでしょう。
【参考文献】
マルセル・モース(吉田禎吾他訳)『贈与論』(1925=2009年、ちくま学芸文庫)
レヴィ=ストロース(福井和美訳)『親族の基本構造』(2000年、青弓社)
河合雅雄『子どもと自然』(1990年、岩波新書)
斎藤環『家族の痕跡』(2010年、ちくま文庫)
原ひろ子『ヘヤー・インディアンとその世界』(1989年、平凡社)
